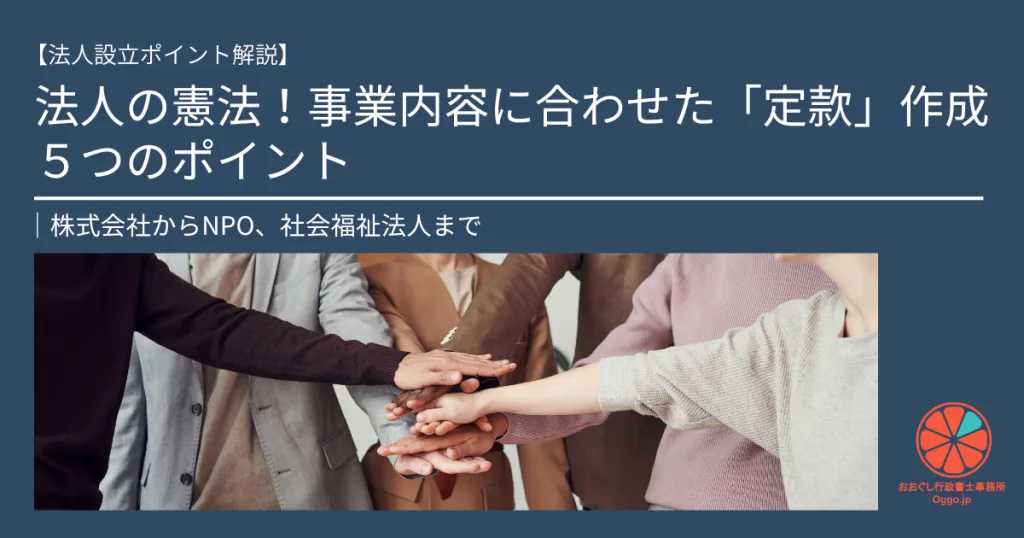【医療機器ポイント解説】申請から取得までのロードマップ:医療機器製造販売業許可
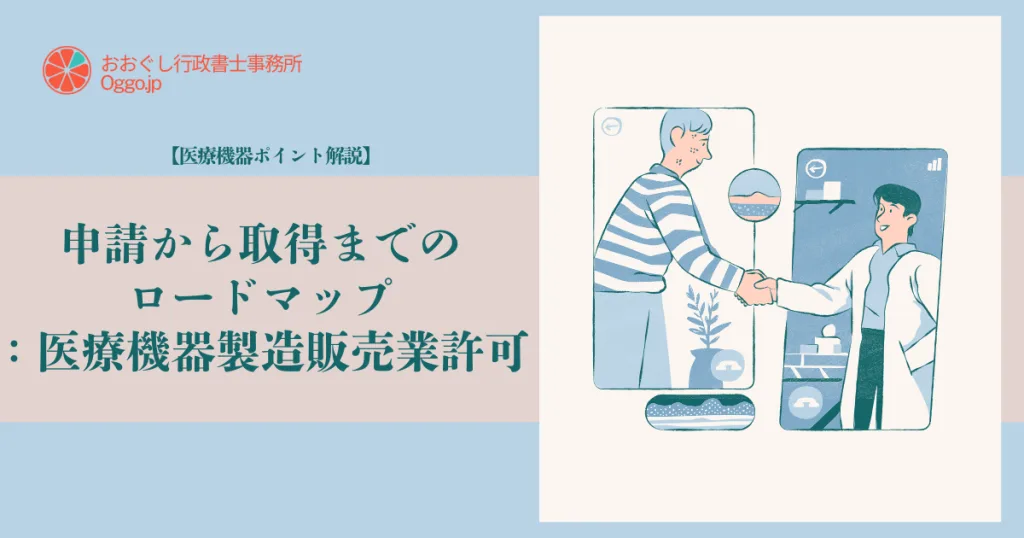
【医療機器ポイント解説】申請から取得までのロードマップ:医療機器製造販売業許可
はじめに
医療機器ビジネスを始めるために、避けては通れない最初の大きな関門が「医療機器製造販売業許可」の取得です。これは、製品を市場に流通させる責任者としての「資格」を得るための許可です。本記事では、これまでの解説を基に、実際に許可を取得するまでの流れを「準備」から「申請」「審査」「許可取得」までの4つのステップに分け、具体的なロードマップとして解説します。
ステップ1:申請前の準備 - 全ての土台を固める
申請は、準備が9割と言っても過言ではありません。以下の体制が整っていることが大前提です。
- ① 医療機器のクラスを決定する
- どのクラスの医療機器を扱うかによって、取得すべき許可の種類(第一種〜第三種)が決まります。
- (<u>【Vol.2】事業の成否を分ける「医療機器のクラス分類」とは?</u>の記事も合わせてお読みください)

こちらの記事も合わせてお読みください:
- ② 「三役(五役)」を設置する
- 総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、安全管理責任者をはじめとする三役(五役)が確保できている必要があります。
- 総括製造販売責任者と国内品質業務運営責任者の資格要件は満たしているか、事前に紹介しておくのが吉です。

こちらの記事も合わせてお読みください:
- ③ QMS/GVP体制を構築する
- QMS体制省令・GVP省令に適合した社内体制(手順書や記録様式の作成など)を構築します。

こちらの記事も合わせてお読みください:
- ④ 申請窓口を確認する
- 申請先は、原則的に主たる機能を有する事務所(本社など)の所在地の都道府県薬務主管課です。
- ⑤ 会社の事業目的を確認する
- 法人の登記事項証明書(登記簿謄本)の「目的」の欄に、「医療機器の製造販売」といった趣旨の記載があるかを確認します。もしなければ、株主総会を開いて定款を変更し、目的を追加する手続きが必要になる場合があります。

こちらの記事も合わせてお読みください:
ステップ2:許可申請 - 必要書類を揃えて窓口へ
準備が整ったら、いよいよ申請です。
- 主な申請書類一覧
- 許可申請書(様式第六十五)
- 申請者の登記事項証明書
- 申請者(法人の場合は役員)が精神機能の障害を有しない旨の診断書
- 総括製造販売責任者の雇用契約書の写し又は使用関係証明書
- 総括製造販売責任者資格要件を証明する書類(卒業証明書や実務経験証明書など)
- QMS省令・GVP省令に適合していることを示す書類(組織図、手順書一覧など)
- 図面、等
- 申請手数料
- 都道府県に納付する手数料が必要です。(金額は都道府県により異なります)
ステップ3:審査 - 書類と実地の両面から
申請後、都道府県による審査が行われます。
- ① 書類調査
- 提出された書類に不備がないか、要件を満たしているかが確認されます。
- ② 実地調査
- 多くの場合、都道府県の担当者が事務所を訪問し、実際に体制が運用可能かを確認します。
- チェックされるポイント(例):
- 提出された図面通りか
- QMS/GVP関連の文書が適切に保管されているか
- 三役(五役)がそれぞれの役割と業務手順を理解しているか(ヒアリング)
- 事務所の独立性が保たれているか
- 期間の目安
- 申請から許可取得までの標準的な期間は、2〜3ヶ月程度ですが、都道府県や申請内容によって変動します。
ステップ4:許可取得!しかし、これはスタートライン
- 許可証の交付
- 審査の結果、問題がなければ許可証が交付され、晴れて医療機器製造販売業者となります。
- 注意点:これは「事業の許可」
- この許可は、あくまで「製造販売業という事業を行ってよい」という許可です。個別の製品を市場に出すためには、この後さらに、製品ごとの承認・認証・届出の手続きが必要になることを強調します。
まとめ:計画的な準備で、スムーズな許可取得を
医療機器製造販売業許可の取得は、多くの要件をクリアする必要がある、計画性が求められるプロセスです。特に、QMS/GVP体制の構築や三役の確保(特に国内品責…!!)には時間がかかります。事業計画の早い段階から専門家と相談し、しっかりとしたロードマップを描くことが、スムーズな事業開始の鍵となります。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。