【医療機器ポイント解説】誰がなる?どんな役割?医療機器の「三役(五役)」を徹底解説
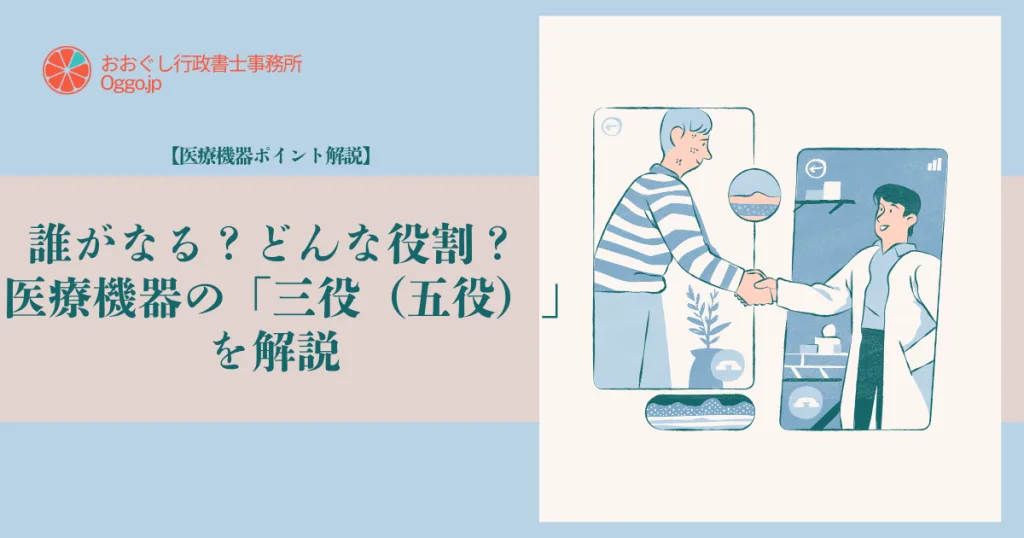
【医療機器ポイント解説】誰がなる?どんな役割?医療機器の「三役(五役)」を徹底解説
はじめに
医療機器の製造販売業許可を取得するためには、前回解説したQMS/GVPといった「仕組み」だけでなく、その仕組みを動かす「人」の要件を満たすことが不可欠です。その中心となるのが、「総括製造販売責任者」「国内品質業務運営責任者」「安全管理責任者」の3つの役職、通称「三役」です。QMS省令はそれに加えて「管理監督者」と「管理責任者」も立てることも要求します。
本記事では、これら三役(五役)のそれぞれの役割、求められる資格、そして兼任の可否など、人的要件のポイントを根拠条文も交えながら分かりやすく解説します。
1. 医療機器事業の人的要件「三役(五役)」とは?
医療機器の製造販売業者は、薬機法に基づき、以下の3つの役職(三役)を設置する義務があります。
- ① 総括製造販売責任者(通称:総責)
- ② 国内品質業務運営責任者(通称:国内品責)
- ③ 安全管理責任者(通称:安責)
これに以下の2つの役職を加え、五役とします。
- ④ 管理監督者
- ⑤ 管理責任者
この五役が、製造販売する医療機器の品質と安全性に責任を負う、事業運営の中心となる存在です。前回解説したQMS(品質管理監督システム)とGVP(安全管理)の仕組みは、この五役がそれぞれの役割を果たすことで初めて実効性を持ちます。

こちらの記事も合わせてお読みください:
2. 三役の具体的な役割と資格要件
まずは実行部隊とも言える三役から紹介差し上げますね。根拠となる法令と共に、具体的に見ていきましょう。
① 総括製造販売責任者 - 事業全体の最高責任者
- 役割: 品責と安責を監督し、医療機器の製造管理と品質管理並びに安全管理(GVP)に関する業務を統括する、文字通り製造販売における総括責任者です。製品の市場への出荷可否の最終決定や、不具合発生時の回収といった安全確保措置の実施について、最終的な責任を負います。 (根拠法令:薬機法 第23条の2の14)
- 資格要件: 総括製造販売責任者になれる資格要件は、取り扱う医療機器のクラスによって異なります。
- 第一種、第二種医療機器製造販売業:高度管理医療機器(クラスⅢ, Ⅳ)まで、または管理医療機器(クラスⅡ)までの取り扱い
- 薬機法施行規則第114条の49第1項第1号
大学等で物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者 - 薬機法施行規則第114条の49第1項第2号
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した後、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 - 薬機法施行規則第114条の49第1項第3号
医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に五年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者 - 薬機法施行規則第114条の49第1項第4号
厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
- 薬機法施行規則第114条の49第1項第1号
- 第三種医療機器製造販売業:一般医療機器(クラスⅠ)の取り扱い
- 薬機法施行規則第114条の49第2項第1号
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者 - 薬機法施行規則第114条の49第2項第2号
旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、生物学、工学、情報学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者 - 薬機法施行規則第114条の49第2項第3号
厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
- 薬機法施行規則第114条の49第2項第1号
- 第一種、第二種医療機器製造販売業:高度管理医療機器(クラスⅢ, Ⅳ)まで、または管理医療機器(クラスⅡ)までの取り扱い
② 国内品質業務運営責任者 - 品質の番人
- 役割:QMS省令に基づき、製品の品質管理業務を統括する責任者です。製造所からの出荷可否の決定、品質に関する情報の評価、品質不良が発生した場合の対応(原因究明や回収の要否判断など)を主導します。 (QMS省令第72条)
- 資格要件: 国内品質業務運営責任者になるには、以下の要件を満たす必要があります(QMS省令第72条第一項)。
- ① 製造販売業者における品質保証部門の責任者であること
- ② 品質管理業務その他これに類する業務に3年以上従事した者であること
- ③ 国内の品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること
- ④ 医療機器等の販売に係る部門に属する者でないことその他国内の品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること
③ 安全管理責任者 - 市販後の安全の番人
- 役割: GVP省令に基づき、製品の市販後安全管理業務を統括する責任者です。医療機関や患者さんから寄せられる不具合などの安全管理情報を収集・検討し、必要に応じて添付文書の改訂や回収といった安全確保措置の立案・実行を主導します。
- 資格要件: 安全管理責任者になるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 第一種医療機器製造販売業:高度管理医療機器(クラスⅢ, Ⅳ)までの取り扱い (GVP省令 第4条)
- ① 安全管理統括部門の責任者であること
- ② 安全確保業務その他これに類する業務に3年以上従事した者であること
- ③ 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること
- ④ 医薬品等の販売に係る部門に属する者でないことその他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること
- 第二種、第三種医療機器製造販売業:高度管理医療機器(クラスⅡ)まで、または一般医療機器(クラスⅠ)までの取り扱い (GVP省令 第13条第2項及びGVP省令大15条による第13条の準用)
- ① 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること
- ② 医薬品等の販売に係る部門に属する者でないことその他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること
3. QMS省令が求めるふたつの重要な役割:「管理監督者」と「管理責任者」
三役とは別に、QMS省令では「管理監督者」と「管理責任者」の設置も求めています。(QMS省令 第16条)
基本的に役員等から選出されることがわかるように、QMS(品質管理監督システム)を運用するために必要な資源(リソース)を管理し、動かすことができる実行力が求められています。
④管理監督者(QMS省令第2条第10項)
- 要件:管理監督者は役員等から、管理職の地位にある者その他これに相当する者のうち選ばれます。特定の学歴や実務経験など要求されません。
- 役割:製造販売業者等の品質管理監督システムに係る業務を最上位で管理監督する
⑤管理責任者(QMS省令第16条)
- 要件:管理責任者は役員、管理職の地位にある者その他これに相当する者のうち選ばれます。特定の学歴や実務経験など要求されません。
- 役割:製造販売業者等の品質管理監督システムの実施及び維持の責任者
4. 三役の「兼任」はどこまで可能か?
特にこれから事業を始める事業者の方にとって、兼任の可否は重要なポイントです。
- 原則:
- 品質をチェックする機能(品責)と、安全性をチェックする機能(安責)は、互いに独立して適切に機能することが求められます。そのため、「国内品質業務運営責任者(品責)」と「安全管理責任者(安責)」の兼任は、原則として認められません。
- 兼任可能なパターン:
- 第三種医療機器製造販売業者については、総括製造販売責任者は、国内品責及び安責の三者の兼務が可能です。(平成26年8月6日薬食発0806第3号第6 その他1(1)ウ)
- 第二種医療機器製造販売業者については、総括製造販売責任者は、国内品責または安責のどちらか一方との兼務ができます。(平成26年8月6日薬食発0806第3号第6 その他1(1)イ)
- 第一種医療機器製造販売業者については、総括製造販売責任者は、国内品責との兼務ができます(平成26年8月6日薬食発0806第3号第6 その他1(1)ア)
- 総括製造販売責任者は、「国内品責」「管理監督者」「管理責任者」を兼ねることが出来ます。(QMS省令第71条第二項)
- 国内品責は、管理責任者を兼ねることができます。(QMS省令第72条第一項)
- 上記以外の場合は平成16年7月9日薬食発第0709004号の第26の1も参照
- 注意点: ただし、兼任する場合であっても、それぞれの役職の責任と業務を適切に遂行できることが大前提です。名ばかりの兼任は認められず、実態として各業務が機能していることが求められます。
まとめ:事業計画の初期段階で「三役(五役)」の人材確保を
医療機器事業は、製品アイデアや資金だけでなく、「人」の要件をクリアして初めてスタートラインに立つことができます。自社が取り扱う予定の医療機器のクラスは何か、それに必要な三役(五役)の要件は何か、そしてその人材をどう確保するのか。これらは、事業計画の極めて早い段階で検討すべき重要事項です。
当事務所では、貴社の事業計画に合わせた必要な人的要件の整理から、候補者の方の資格要件の確認、そして許可申請からその後までをサポートいたします。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。