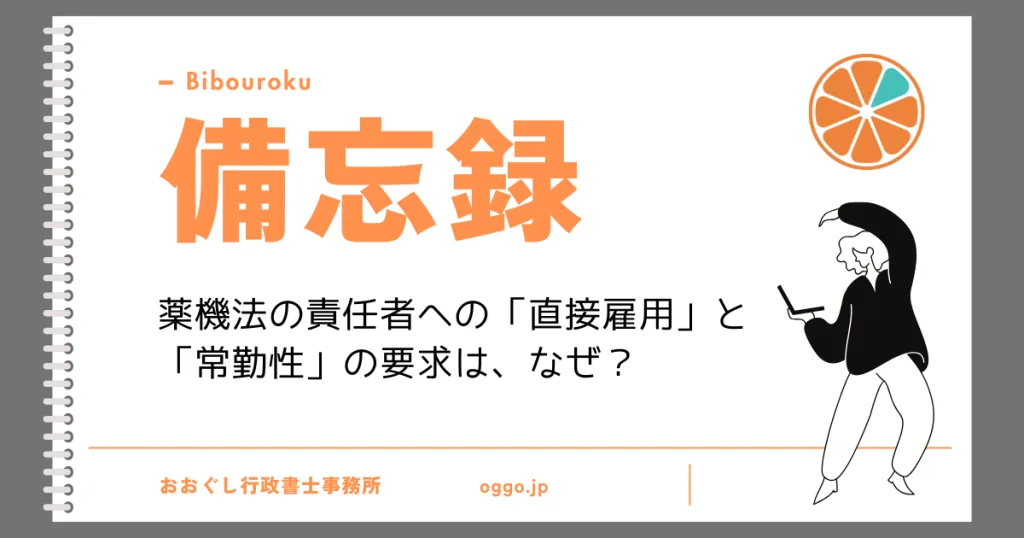【化粧品ポイント解説】化粧品保管で事業拡大!倉庫業者が知るべき「化粧品製造業許可」取得の3ステップ
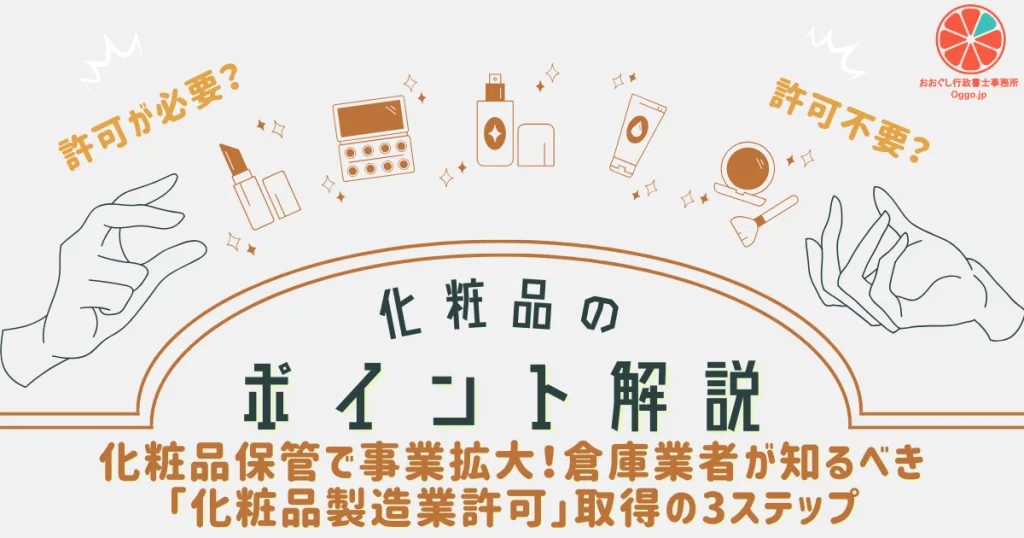
【化粧品ポイント解説】化粧品保管で事業拡大!倉庫業者が知るべき「化粧品製造業許可」取得の3ステップ
EC市場の活況を背景に、化粧品輸送・保管の需要はますます高まっています。倉庫業者の皆様にとって、化粧品は非常に魅力的な商材の一つであり、大きな事業拡大のチャンスです。
「『うちの倉庫は、ラベル貼りやセット組も含めて化粧品を扱えます』と、自信を持って提案したい」 「化粧品という新たな商材に対応し、事業の柱を育てたい」
この記事は、そうお考えの皆様を応援するためのものです。化粧品関連の業務範囲を広げるために必要な「化粧品製造業許可」について、許可が不要なケースと必要なケースの違いを明確にし、許可取得に向けた具体的な3つのステップを分かりやすく解説します。
まず確認!その業務、「許可」は必要ですか?
すべての化粧品保管に、化粧品製造業許可が必要なわけではありません。ポイントは、倉庫に保管する物が、製造が完了している最終製品なのか、製造途中の半製品なのかどうかです。
許可が【不要】なケース
- すでに市場に出荷できる最終製品を、そのまま保管し、出荷する場合
消費者に届く状態(容器や箱に包装・表示済み)の製品を、荷主の指示に従って預かり、そのまま出庫するだけであれば、許可は不要です。これは、一般的な倉庫業の範囲内で行える業務です。
許可が【必要】となるケース
- 製造途中の半製品を取り扱う場合
製造工程が完了していない化粧品を取り扱えるのは、事前に製品ごとに届け出ている「化粧品製造業許可業者」のみです(薬機法)。薬機法における製造工程には、「包装」「表示」「検査」「(製造工程中の)保管」といった工程が含まれます。
そのため、以下のような行為を倉庫内で行う場合には、許可と製品ごとの届出が必要となります。
- 複数の製品を詰め合わせセットにするアッセンブリー作業(消費者は詰め合わせセットとして購入する)。
- 輸入した化粧品に、日本語の成分表示ラベル(法定ラベル)を貼り付ける。
- 化粧品の化粧箱が汚れていたので、きれいな化粧箱に入れ替える。
- ロット番号が消えかけていたので、油性ペンで見やすく追記する。
- 化粧品の表示に間違えがあったので、修正ラベルを貼り付ける。
- 「製造販売業者による出荷判定」が終わっていない物(=製造工程途中の半製品です)をたとえ指一本触れずにただ預かるだけでも…。
これまで「最終製品を預かるだけ」だった倉庫が、荷主から「うちの半製品を一時的に保管してほしい」「ラベル貼りもお願いできないか」といった多様な要望に応えるためには、この許可取得が事業拡大の鍵となります。
ステップ1:許可取得の「カギ」となる要件を理解する
自社の業務に許可が必要だと判断されたら、次に進みましょう。化粧品製造業許可(包装・表示・保管)を取得するために、倉庫に求められるハード(構造設備)とソフト(人的要件)の両面を理解することが「カギ」となります。
1-1. 倉庫に求められる構造設備(ハード面)
管轄の行政(都道府県の薬務課など)による実地調査では、以下の点をはじめとして構造設備がチェックされます。
- 衛生的な保管環境か?
- 製品を床に直接置かない構造(パレットなど)になっているか。
- 防虫・防鼠対策が講じられているか。
- 清掃がしやすく、衛生状態を保てるか。
- 品質管理は万全か?
- 化粧品とそれ以外の物を明確に区分して保管できるか。
- 不良品や回収品を区別して保管する場所が確保されているか。
1-2. 必要な人材(ソフト面)
ここが皆さん、一番苦労するところです…。許可を取得する事業所には、以下の責任者の設置が義務付けられています。
- 責任技術者: 製造所の責任者として、構造設備や手順書が基準に適合しているかを管理します。
この責任者には次のような資格要件があります。要件を満たす人材が社内にいない場合は、新たに採用する必要があります。
・施行規則第91条第2項
法第17条第10項に規定する化粧品の製造所の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 薬剤師
二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

こちらの関連記事では、「常勤性」や「兼務」について言及してます。あわせてご確認ください。
ステップ2:申請書類の作成と提出
要件を確認したら、次は行政に提出する申請書類の準備です。主に以下のような書類が必要となります。
- 許可申請書
- 倉庫の平面図
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 責任技術者の資格を証明する書類
- など
ステップ3:行政による実地調査への対応
申請書類が受理されると、管轄の行政担当者が倉庫を訪れ、申請内容と実際の状況が一致しているかを確認する「実地調査」が行われます。
調査当日は、作成した業務手順書に沿って業務が行われていることを具体的に説明する必要があります。指摘事項があれば、改善計画を立てて報告し、許可取得を目指します。
化粧品保管事業への第一歩、専門家と共に
化粧品保管倉庫への事業拡大は、貴社の可能性を大きく広げるチャンスです。許可取得には専門的な知識と準備が不可欠ですが、それは同時に、参入障壁となり貴社の強みともなり得ます。許可を取ったら、化粧品の製造販売業者との取り決め書の原案なども自社で作っておくことをお勧めします。
「許可取得の要件をクリアし、新たな事業の柱を育てたい」 「スムーズに許可を取得し、一日でも早く事業を始めたい」 「専門家のアドバイスを受け、万全の体制で臨みたい」
当事務所は、そのような前向きな想いを全力でサポートいたします。行政書士は、許認可申請の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なステップをご提案し、許可取得までをスムーズに後押しし、許可取得後も身近なアドバイザーとしてあなたの事業をます。
まずは、お電話または下記のお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。