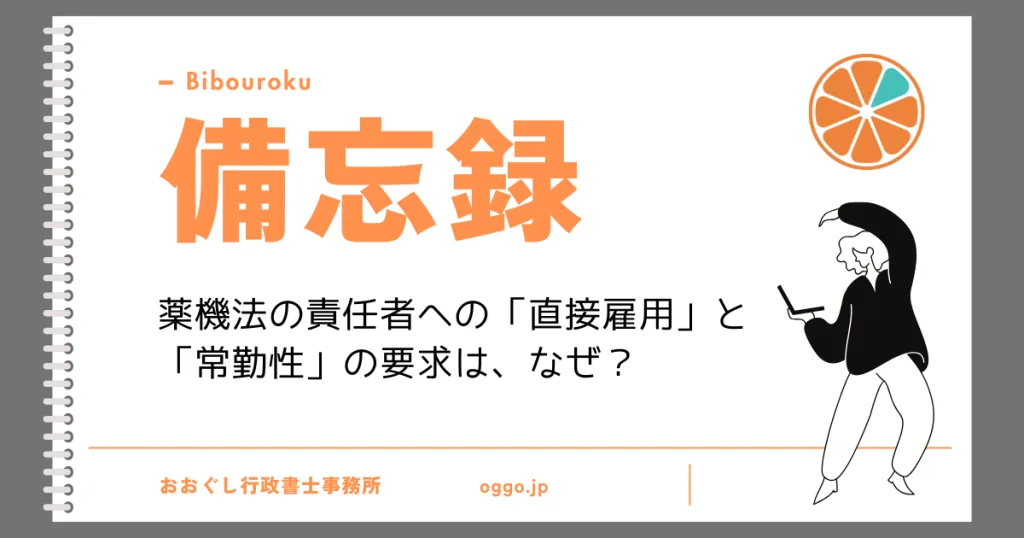【化粧品ポイント解説】物流コスト削減と業務効率化へ!自家倉庫で化粧品を扱うための薬機法ガイド
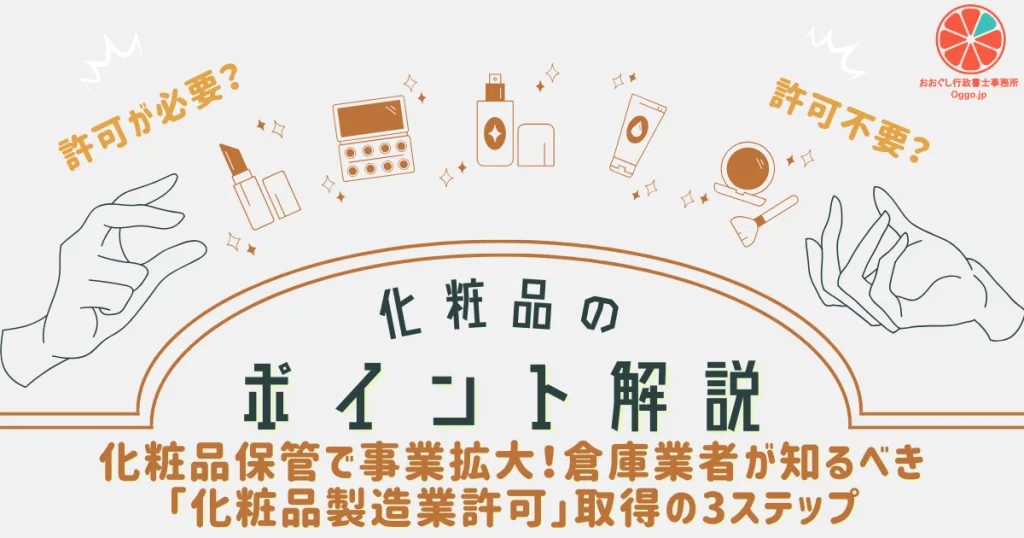
【化粧品ポイント解説】物流コスト削減と業務効率化へ!自家倉庫で化粧品を扱うための薬機法ガイド
輸入した化粧品へのラベル貼り、複数商品を組み合わせたセットアップ、サンプルのアッセンブリー作業、はたまた汚れた化粧箱の入れ替え。これらの業務を外部の許可倉庫に委託しており、「自社の倉庫で、もっと柔軟に対応できれば…」と感じたことはありませんか?
実は、医薬品医療機器等法(薬機法)で定められた「化粧品製造業許可(包装・表示・保管)」を取得すれば、貴社の倉庫でこれらの業務を行うことが可能になります。外部委託費を削減し、自社でスピーディーに製品を市場に出す体制を整えることは、大きな競争力となります。
この記事では、自家倉庫の活用を目指す化粧品事業者の皆様のために、許可取得のポイントを分かりやすく解説します。
まず確認!その業務、自社倉庫で行うには「許可」が必要ですか?
貴社が自社倉庫で行いたい業務は、許可が必要な「製造」行為に当たるでしょうか。ポイントは、扱う製品が「出荷判定済み製品」か「出荷判定前の半製品」か、という点です。
許可が【不要】なケース
- 総括製造販売責任者による市場への出荷判定が済んでいる製品を、そのまま保管し、出荷する場合
すでに法定表示が完了し、包装された製品を、ECサイトの注文に応じて発送したり、小売店に出荷したりするだけであれば、許可は不要です。
許可が【必要】となるケース
- 出荷判定が済んでいない半製品を取り扱う場合
薬機法では、出荷判定が済んでいない=製造工程中の半製品です。これを取り扱えるのは、化粧品製造業許可を持つ事業者に限られています。 そのため、自社の倉庫で以下のような業務を行うには、許可が必要です。
- 複数の製品を詰め合わせセットにするアッセンブリー作業(消費者は詰め合わせセットとして購入する)。
- 輸入した化粧品に、日本語の成分表示ラベル(法定ラベル)を貼り付ける。
- 化粧品の化粧箱が汚れていたので、きれいな化粧箱に入れ替える。
- ロット番号が消えかけていたので、油性ペンで見やすく追記する。
- 化粧品の表示に間違えがあったので、修正ラベルを貼り付ける。
- 「製造販売業者による出荷判定」が終わっていない物をたとえ指一本触れずにただ預かるだけでも…。
自家倉庫での許可取得!3つの重要ポイント
自社の倉庫で許可を取得するためには、主に「構造設備」「人的要件」「申請準備」の3つのポイントをクリアする必要があります。
ポイント1:倉庫の構造設備(ハード面)
行政による実地調査では、倉庫が化粧品を衛生的に、かつ品質を損なうことなく保管できる状態かどうかがチェックされます。
- 衛生管理: 製品を床に直接置かない、防虫・防鼠対策がされている、清掃しやすいなど。
- 品質管理: 半製品と最終製品、良品と不良品などを明確に分けて保管できるスペースがあるか。
既存の倉庫を改修して対応することも可能です。どの程度の準備が必要か、専門家がアドバイスします。
ポイント2:責任技術者の設置(ソフト面)
許可を取得する倉庫(製造所)には、「責任技術者」を1名設置する必要があります。
責任技術者には、薬剤師や特定の学歴(化学・薬学など)といった資格要件があります。化粧品事業に携わっている貴社であれば、品質管理部門などに要件を満たす方が在籍している可能性があります。
・施行規則第91条第2項
法第17条第10項に規定する化粧品の製造所の責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 薬剤師
二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

こちらの関連記事では、「常勤性」や「兼務」について言及してます。あわせてご確認ください。
ポイント3:申請書類の準備と提出
許可申請書や倉庫の平面図といった、定められた書類を準備して行政へ提出します。
申請が受理されると、後日、実地調査が行われます。この調査では、主に「ポイント1」で解説したような構造設備が、申請内容と相違ないかどうかが現場で確認されます。
自社一貫体制で、ビジネスを次のステージへ
外部倉庫への委託料、輸送コスト、コミュニケーションの手間…。自家倉庫で化粧品の包装・表示・保管まで行えるようになれば、これらの課題を解決し、より迅速で柔軟な事業運営が可能になります。
「うちの倉庫でも許可は取れるだろうか?」 「責任者になれる社員がいるか確認したい」 「何から準備を始めたらいいか分からない」
当事務所は、そんな化粧品事業者の皆様を力強くサポートします。許認可申請の専門家として、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案し、許可取得、そしてその先の事業成長までを共に目指します。
まずは、お電話または下記のお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。