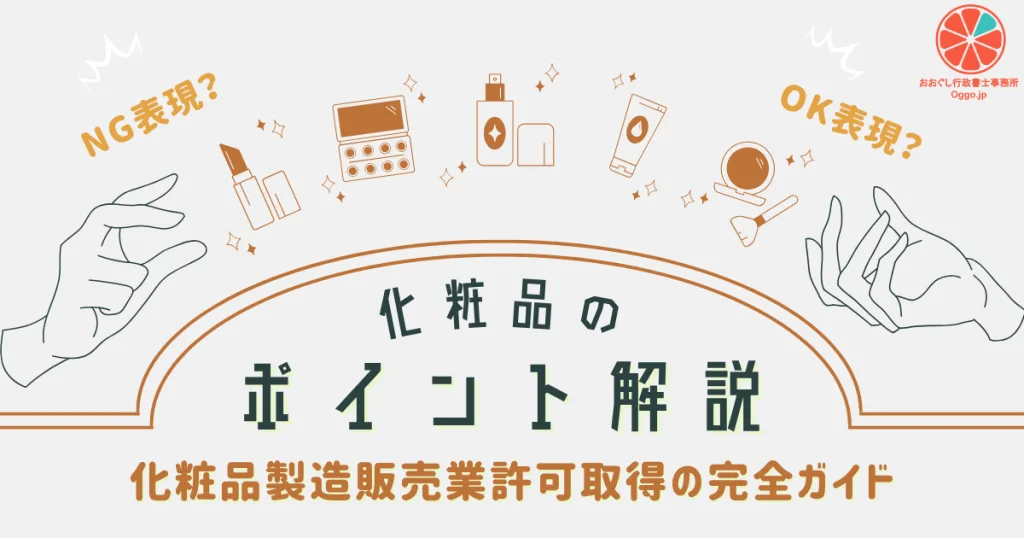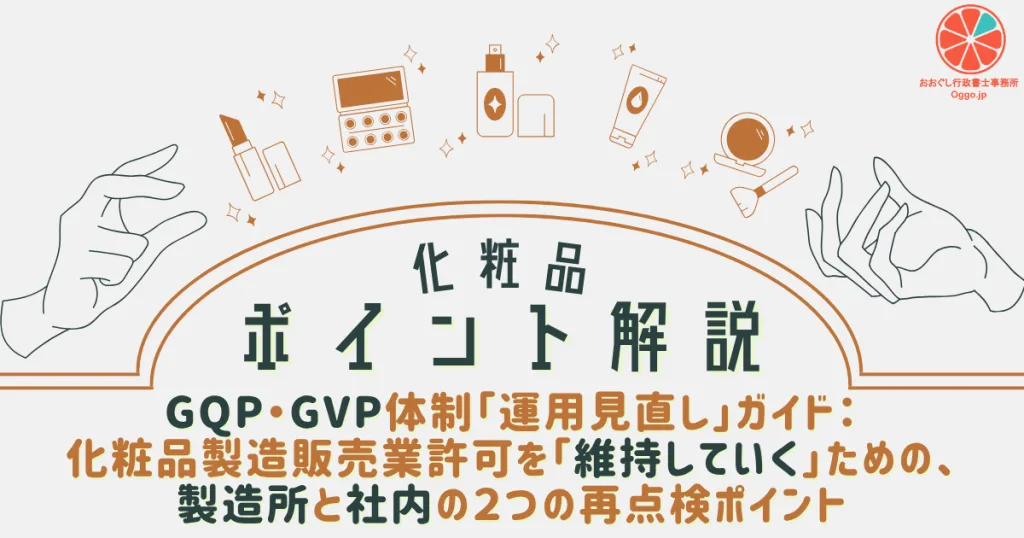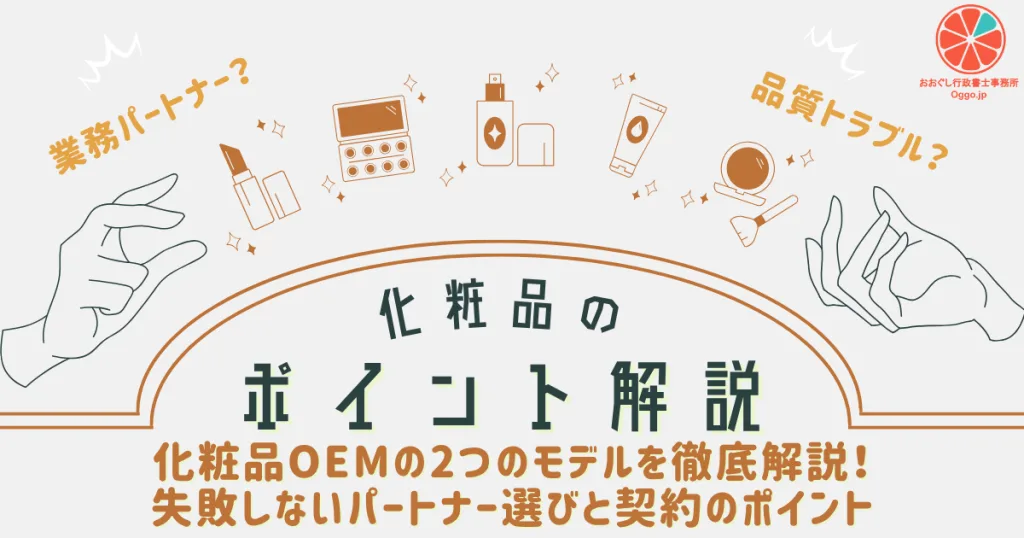GQP・GVP体制「構築」ガイド:化粧品製造販売業許可を「これから取得」するための、体制構築の本質理解と5ステップ
化粧品製造販売業許可を取得し、事業を継続する上で、避けては通れないのが「GQP」と「GVP」という2つの基準です。これらは単なる申請のための書類ではなく、製品の品質と安全性を守り、お客様からの信頼を築くための根幹となる仕組みです。
しかし、「省令は複雑で、何から手をつければいいかわからない」と感じる事業者様も少なくないでしょう。
この記事では、化粧品ビジネスに特化し、GQP(品質管理基準)とGVP(製造販売後安全管理基準)の体制をゼロから構築するための具体的なステップを、手順書の作成から日々の運用、そして実用的なチェックリストまで、法的根拠を交えて分かりやすく解説します。
化粧品の品質と安全を守る3ルールを知る:GQPとGVP、そしてGMP
化粧品の品質と安全は、この3つの柱が連携することで成り立っています。それぞれの役割を正しく理解することが、体制構築の第一歩です。
これら3つは、「GVP(市場からの声)→ GQP(司令塔での評価・指示)→GMP(製造現場での改善)」、あるいは「GMP(製造現場での逸脱)→ GQP(司令塔での出荷判断・指示)→ GVP(必要に応じた市場での安全確保措置)」というように、常に情報をやり取りし、連携することで機能する一つの大きなシステムです。
GQP概要
- 用語としてのGQP:Good Quality Practice:品質管理基準
- 製造販売業者の許可要件としてのGQP
- 省令の正式名称:「医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令」(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)
- 目的: 品質管理の基準を定めることにより、流通する製品の品質を確保すること 。
- 行うべき業務: 市場への出荷管理、製造業者等の管理監督、品質情報の処理、回収処理など。化粧品についてはGQP省令第4章(第18条、第19条)で、製造販売業者が行うべき具体的な業務内容が定められています。
- 担当部署の立ち位置:製造販売業者の「品質保証の司令塔」です。 製造業者がGMPに基づき正しく製品を製造しているか管理監督し、最終的に市場へ出荷してよいかどうかの可否を判断する、極めて重要な役割を担います。
GVP概要
- 用語としてのGVP:Good Vigilance Practice:製造販売後安全管理基準
- 製造販売業者の許可要件としてのGVP
- 省令の正式名称:「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)
- 目的概要: 製品の製造販売後安全管理の基準を定めることにより、安全確保を行うこと
- 行うべき業務: 安全管理情報の収集、検討、その結果に基づく安全確保措置の実施など。化粧品については第3章で、製造販売業者が行うべき具体的な業務内容が定められています。その中心となるのが「品質管理業務手順書」の作成と、それに基づく業務の実施です。
- 担当部署の立ち位置:製造販売業者の「市販後の安全監視塔」です。 市場に出た製品について、お客様からの声(副作用情報など)を収集・評価し、安全性に問題がないかを見守り、必要に応じて迅速な対応(回収など)を行うための仕組みです。
- 備考:化粧品はGVP省令第3条に基づき「第三種製造販売業者」に分類され、医薬品等と比較して一部の要求事項が緩和されていますが、これらの体制構築が許可要件であることに変わりはありません。
GMP概要
- 用語としてのGMP:Good Manufacturing Practice:適正製造規範
- 製造業者の許可要件としてのGMP
- 化粧品においてGMPは法律で定められた許可要件ではありません。
- 化粧品業界の自主基準としてのGMP
- Cosmetics Good Manufacturing Practice:化粧品適正製造規範
- 製造業者の「製造現場のルール」
- 国際規格である「ISO 22716」が化粧品GMPのガイドラインとして広く知られており、多くの製造業者がこの規格に沿って品質管理を行うなど、業界の自主的な取り組みとして定着しています
製造販売業者(GQP)と製造所(GMP)の責任範囲
製造販売業者は、GQP体制に基づき、製造所がGMPを遵守して適切に製造しているかを管理・監督する「責任」を負います。製造を委託(OEM)していても、その責任は免除されません。
なぜGQP/GVPが必要か?- 平成17年薬事法改正の意図
化粧品の品質を担保するためのGQP、GVP、GMPで構成されるシステム。この仕組みの根幹を理解するには、平成17年(2005年)の薬事法改正に遡る必要があります。この改正によって、製品の市場に対する最終責任を負う「製造販売業者」と、製品を実際に作る「製造業者」の役割が法的に分離されました。
この「製販分離」により、製造販売業者は自社工場を持たなくても、製品の企画・販売に特化できるようになりました。しかしそれは同時に、自社の目が届きにくい外部の製造業者を、いかに管理監督して品質を保証するか、という新たな責任を生んだのです。 この、製造販売業者が司令塔として製造業者を管理監督するための仕組みが「GQP」であり、市場に出た後の製品の安全に責任を持つための仕組みが「GVP」なのです。
GQP・GVP体制構築の「5つのステップ」
ここでは、製造販売業許可業者に必要なGQP・GVP体制をゼロから構築する手順を、5つのステップで解説します。
ステップ1:3役の「責任者」を設置する
まず、体制の核となる「人」を配置します。いわゆる「三役」がこれです。
- 総括製造販売責任者(総括): GQP/GVP体制全体の最高責任者。薬機法第17条第1項に基づき設置が義務付けられています。品責・安責を監督し、製品の品質と安全に関する最終判断を行います。品質不良や安全に関する問題が発生した際には、品責・安責らの報告に基づいて回収などの最終的な措置を決定し、実行を指示します。
- 品質保証責任者(品責): GQP(品質保証)の実務を統括する責任者。品質管理業務を統括し、その業務が適正かつ円滑に行われているかを確認します。また製造所の管理や出荷可否の判断実務も担います。 GQP省令第18条第2項に基づき、「品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者」を置く必要があります。販売部門から独立していることが求められます(GQP省令第4条第3項第四号の準用)。化粧品の場合、医薬品ほど厳格な経験年数は求められません。
- 安全管理責任者(安責): GVP(安全管理)の実務を統括する責任者。クレームや副作用情報などの安全管理情報の収集から評価、安全確保措置の立案までの管理実務を担います。GVP省令第13条の2第2項に基づき設置が義務付けられています。販売部門からの独立性も同条項で要求されています 。
2025年改正薬機法情報
現行法では品責・安責の設置は省令で定められていますが、2025年中に施行が見込まれる改正薬機法により、これらの責任者の設置は法律上の直接的な義務へと格上げされます。企業のガバナンス強化が一層求められることになります 。
なお、化粧品事業における責任者の要件及び兼務に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
また、総括についてはこちらの備忘録記事もございます。
ステップ2:GQP手順書(品質管理業務手順書)を作成する
GQP(品質保証)のルールブックとして「品質管理業務手順書」を作成します。GQP省令で定められた業務をどのように行うか、具体的なルールを落とし込みます。GQP省令第18条第1項に基づき、化粧品事業者は以下の6項目を盛り込む必要があります。
- 市場への出荷に係る記録の作成に関する手順: どのロットの製品を、いつ、どこへ出荷したのかを記録する手順。これにより、製品のトレーサビリティを確保し、万が一の回収時に迅速な対応を可能にします。
- 適正な製造管理及び品質管理の確保に関する手順: 製造を委託するOEMメーカー等が、契約通りに、かつ適正な品質管理下で製造していることを、どのように確認・管理監督するかの手順です。製造業者との「取決め」がこの中核をなします。
- 品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順: お客様からのクレームなど、製品の品質に関する情報を得た場合に、どのように評価し、原因を究明し、改善措置を講じるかを定めます。
- 回収処理に関する手順: 製品の品質不良などにより、市場から製品を回収する必要が生じた場合に、誰が判断し、どのように実施するかの手順です。
- 文書及び記録の管理に関する手順: 作成した全ての文書や記録を、どのように承認・改訂・保管するかを定めます。化粧品の場合、記録の保管期間は原則5年間と定められています。
- その他必要な品質管理業務に関する手順: 上記以外に、自社の品質管理に必要な業務(例:自己点検、教育訓練、責任者間の連携など)を定めます。
これらの手順書は、総括が業務を行う事務所に備え付けなければなりません 。(GQP省令第18条第3項)
ステップ3:GVP手順書(安全管理業務手順書)を作成する
GVP省令において、化粧品は第三種製造販売業者に分類され、医薬品に比べて要求事項が緩和されています。 しかし「市販後の安全性を確保する」という本質的な目的を達成しなくてもいい、というわけでは当然ありません。
化粧品事業者に手順書の作成は明示的に義務付けられていません。しかし、関連通知(逐条解説)ではその整備が求められており 、GVP省令第13条の2で要求される業務を遂行し、許可要件を満たしていることを示す上で、手順書の作成は実務上不可欠です 。医薬品の基準を参考に、少なくとも以下の内容を盛り込みましょう。
- 安全管理情報の収集に関する手順
- 安全管理情報の検討及び安全確保措置の立案に関する手順
- 安全確保措置の実施に関する手順
- 総括への報告に関する手順
- 品質保証責任者(品責)との連携に関する手順
【ポイント】この手順書を使い、達成すべきこと3つ
- 安全管理情報の収集:お客様や医療関係者、国内外の文献や政府機関など、あらゆる情報源から自社製品の安全性に関する情報(肌トラブル、アレルギー報告など)を能動的に収集し、記録します。
- 情報の検討と安全確保措置の立案:収集した情報を遅滞なく検討し、製品の安全性に影響を与える可能性があるかを評価します。 評価の結果、必要と判断すれば、回収、販売停止、情報提供といった安全確保措置を立案し、総括製造販売責任者へ報告します。
- 安全確保措置の実施:総括製造販売責任者が、報告された措置案を評価し、実施を決定します。 安全管理責任者はその指示に基づき、GQP部門とも連携しながら、迅速に措置を実施し、その結果を記録・報告します。
ステップ4:製造所(OEM先)と「取決め書」を締結する
GQP体制(製造販売業者)とGMP体制(製造所)を連携させるため、製造委託先と「品質に関する取決め書(品質合意書)」を締結します。これはGQP省令第19条で準用される第7条に基づく義務です。
ポイント:
- 逸脱や変更が発生した際、製造所からGQP部門へ速やかに報告・承認を求めるフローを明確化
- GQP部門による製造所への監査権限を明記
ステップ5:文書・記録の管理体制を整える
手順書(ルール)を作成したら、そのルール通りに業務を行い、「記録」を残す体制を整えます。許可申請時や行政の査察(立入検査)では、これらの記録が適切に保存されているかが厳しくチェックされます。
全体について
- 文書の改訂: 手順書などを改訂した場合は、日付と改訂履歴を保存します
- 保存期間: 化粧品の場合、GQPに関する文書および記録はGQP省令第19条(第16条第2項準用)に基づき、GVPに関する記録はGVP省令第16条に基づき、原則として作成の日(手順書等は使用しなくなった日)から5年間保存しなければなりません 。
- 電磁的記録: GQP・GVPともに、文書や記録は電磁的記録(データファイルなど)により作成・保存することが認められています
- GQP業務の記録: GQP省令第18条第2項に基づき、日々の業務(市場への出荷管理、製造業者の管理、品質情報の処理、回収など)を手順書に従って行い、その記録を作成します。
- GVP業務の記録: GVP省令第13条の2に基づき、安全管理情報の収集、検討、措置の実施について記録を作成します。
GQP文書についてのポイント
日々の業務の実施(GQP省令 第18条第2項)
手順書を作成したら、それに基づき日々の業務を遂行し、記録を残します。特に重要なのは、製造販売しようとする製品が、製造業者において適正かつ円滑に製造されたものであることを確認し、その記録を作成することです。これは、製造業者任せにするのではなく、製造販売業者自身が主体的に関与し、品質を保証する責任があることを示しています。
- 市場への出荷管理: 製品を出荷する際に、ロットごとに記録を作成します 。回収時に迅速な対応ができるよう、ロットに関する記載が望ましいとされています 。
- 製造業者の管理: 製造を委託している製造業者が、適正な管理体制のもとで円滑に製造していることを確認し、その記録を作成します 。
- 品質情報の処理: お客様などから製品の品質に関する情報を得たときは、人の健康への影響を評価し、原因を究明します。改善が必要な場合は所要の措置を講じ、その記録を作成しなければなりません 。
- 品質不良・回収: 品質不良またはそのおそれがあると判断した場合は、総括の指示のもと、回収などの必要な措置を速やかに実施し、その記録を作成します 。
GVP文書についてのポイント
- 安全管理情報の収集: 医療関係者、消費者、学会報告、外国政府など、様々な情報源から製品の安全性に関する情報を収集し、その記録を作成します 。品質に関する情報も安全管理情報に含まれるため、品責との密接な連携が必要です 。
- 情報の検討と措置の立案: 収集した情報を遅滞なく検討し、その結果を記録します 。検討の結果、必要があると判断すれば、廃棄、回収、販売停止、添付文書の改訂といった安全確保措置を立案します 。
- 総括への報告と措置の決定: 立案した安全確保措置案を、総括へ文書で報告します 。総括は報告された案を評価し、実施すべき安全確保措置を決定します 。
- 安全確保措置の実施: 総括の指示に基づき、安責が安全確保措置を実施し、その結果を記録・保管します 。措置の結果は、再度、総括へ文書で報告されます 。
実践的!GQP・GVP体制構築チェックリスト
体制構築の際に、抜け漏れがないかを確認するためにご活用ください。
GQP体制チェックリスト
- 品質保証責任者(品責)は任命されていますか?
- 品責は販売部門から独立していますか?
- GQP手順書(市場出荷、製造管理、品質情報、回収、文書管理など6項目)は作成され、事務所に備え付けられていますか?
- 製造業者等との間で、品質に関する取り決めが文書化されていますか?
- 製品のロットごとに出荷記録を作成する手順になっていますか?
- 品質不良やお客様からのクレーム発生時の対応フロー(原因究明、改善措置、総括への報告)は明確ですか?
- 回収処理の手順は定められていますか?
- GQPに関する全ての文書・記録を5年間保存するルールになっていますか?
GVP体制チェックリスト
- 安全管理責任者(安責)は任命されていますか?
- 安責は販売部門から独立していますか?
- GVP手順書(安全管理情報の収集、検討、措置の立案・実施など)は作成されていますか?
- お客様や医療関係者等からの安全管理情報を収集する仕組みはありますか?
- 収集した情報を検討・評価し、必要な安全確保措置を立案する手順は明確ですか?
- 安全確保措置の案を総括に報告し、その決定に基づき措置を実施するフローになっていますか?
- 品責と安責が相互に連携する手順は明確ですか?
- GVPに関する全ての記録を5年間保存するルールになっていますか?
形骸化させないために ー 体制構築後の「運用」こそが重要
GQP・GVP体制の構築は、一度行えば終わりではありません。これらは、企業の品質・安全文化の土台となる「生きたシステム」ですから、企業活動に根付いた「品質文化(クオリティカルチャー)」まで育てていく必要があります。
この品質文化を醸成し、GQP・GVPを形骸化させないための具体的な活動が、「自己点検」と「教育訓練」です。
- 自己点検(内部監査): GQP省令第19条(第14条準用)では、品質管理業務について定期的な自己点検を求めています。これは、問題が起きてから対処するのではなく、問題が起きる前にリスクの芽を発見し、継続的に業務を改善していくための活動です。客観性を担保するため、原則として点検者自身が従事する業務を点検すべきではないとされています。
- 教育訓練: 担当者がGQP・GVPの本質を理解し、なぜその手順が必要なのかを納得して業務にあたることが、システムの形骸化を防ぎます。教科書的な内容だけでなく、具体的な失敗事例などから学ぶ研修を計画的に実施し、記録を残すことが重要です。GQP省令第19条(第15条準用)に基づき、品質管理業務に従事する者に対して、必要な教育訓練を計画的に実施し、記録を残すことが義務付けられています。
近年の事故事例の根本原因として、生産性を優先するあまり、品質管理のルールが軽視される「企業風土」があったと指摘されています。 品質文化は一朝一夕で醸成されるものではありませんので、日々コツコツと積み上げていきましょう。
すでに許可を取得し、既存のGQP/GVP体制の「運用見直し」や「実効性」の確保に関心がある方は、こちらの応用編記事をご覧ください。
化粧品OEM契約における「製造販売業者」の具体的な責任については、こちらの記事もご参照ください。
まとめ:GQP・GVPは、ビジネスの持続可能性を支える生命線
GQP・GVPは、単なる規制対応ではなく、お客様からの信頼を獲得し、長期的なビジネスの持続可能性を確保するための、攻めの「品質保証システム」でもあります。
製造販売業者は、自社が品質保証の司令塔であることを自覚し、GQPを通じて製造現場の化粧品GMPを管理監督し、GVPを通じて市場の声を真摯に受け止める。このGQP・GVP・GMPの「相関」を正しく理解し、全社的な品質文化として根付かせることが、変化の激しい時代において、お客様と社会から選ばれ続けるブランドを築くためのひとつの道と言えるでしょう。
おおぐし行政書士事務所では、事業の規模や実態に合わせたGQP/GVP手順書の作成支援から、許可申請、責任者の要件確認、製造所との「取決め書」作成支援まで、ワンストップでサポートを提供しております。
「自社の場合は、どのような体制が必要か相談したい」 「手順書のひな形ではなく、実務に即した内容で作成したい」
このようなご要望がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。