【法人設立ポイント解説】法人の憲法!事業内容に合わせた「定款」作成5つのポイント
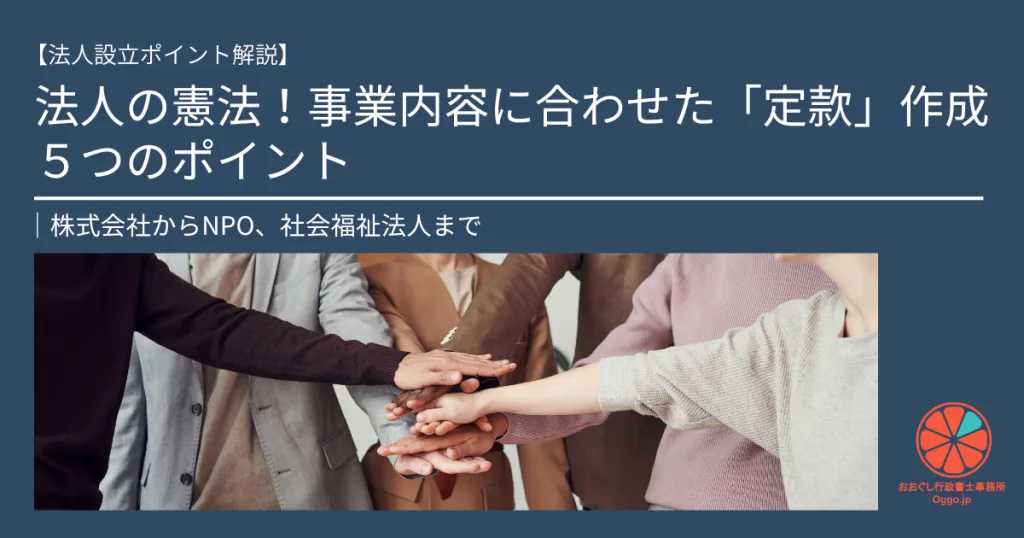
【法人設立ポイント解説】法人の憲法!事業内容に合わせた「定款」作成5つのポイント
はじめに:定款は法人の「憲法」、なぜ重要?
法人設立の手続きを進めると、必ず「定款(ていかん)」という書類を作成します。これは株式会社や合同会社といった営利法人はもちろん、一般社団法人やNPO法人といった非営利法人であっても、必ず作成が義務付けられています。では、この定款とは一体何でしょうか?
一言でいうと、定款は法人のルールブックであり、最も重要な法律である「憲法」にあたるものです。法人の名前(名称)から、事業内容、役員の決め方、運営のルールまで、組織と運営に関する根本原則がすべてこの定款に定められます。
設立時に何となく作ってしまった定款が、将来の事業拡大の足かせになったり、許認可が取得できない原因になったり、融資の審査に影響したり…。そんな事態を避けるため、法人の「憲法」作りで押さえておくべき5つの重要ポイントを解説します。
ポイント1【名称(商号)】:法人の「顔」。ルールを守って慎重に
法人の「顔」となる大切な名前です。営利法人では「商号」、非営利法人では「名称」と呼ばれますが、好きな名前を自由につけられる一方で、いくつか共通のルールがあります。
- 使える文字・記号: 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字(0~9)のほか、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」といった一部の記号も使えます。
- 法人格の明記: 株式会社、合同会社のほか、「一般社団法人」「特定非営利活動法人」「社会福祉法人」といった法人格を、名称の前か後ろに必ず入れなければなりません。
- 同一名称・同一事務所の禁止: 同じ住所に、同じ名称の法人を登記することはできません。
- 類似名称に注意: 登記自体は可能でも、有名企業や団体と紛らわしい名称をつけてしまうと、不正競争防止法などの法律に基づき、損害賠償を請求されるリスクがあります。事前にインターネットや登記情報提供サービスで調査することが重要です。
ポイント2【事業目的】:将来の展開と「許認可」を見据えた生命線
定款に記載された「事業目的」の範囲内でしか、法人は事業を行うことができません。これは定款作成において最も専門的な知識が要求される項目の一つです。
- 具体性・明確性: 誰が見ても何をやっている法人か分かるように、具体的に記載する必要があります。
- 将来性: 現在の事業だけでなく、1~2年以内に始める可能性のある事業もあらかじめ記載しておきましょう。後から追加するには、登記変更の手続きと費用(登録免許税など)がかかります。
- 許認可との関連: 建設業や飲食業といった営利事業だけでなく、介護保険事業や障害福祉サービスといった非営利事業でも、行政の許認可(指定)が必要なものは数多くあります。その場合、許認可の要件を満たす事業目的が定款に記載されていなければ、申請が受理されません。
ポイント3【主たる事務所(本店所在地)】:どこに置く?メリット・デメリット
法人の公式な住所です。会社法では「本店所在地」、多くの非営利法人では「主たる事務所」と呼ばれます。
- 自宅: 自宅を主たる事務所にすることも可能です。メリットは家賃がかからないこと。デメリットは、登記情報に自宅住所が公開されるため、プライバシーの問題が生じる可能性があることです。ただし、近年、プライバシー保護の観点から法改正が進み、株式会社の代表取締役等の自宅住所を非公開にできる制度が始まっています。
- 賃貸物件: 賃貸オフィスやマンションを事務所にする場合、契約書で事業・法人活動での利用が許可されているか、法人登記が可能かを確認し、オーナーの承諾を得ておく必要があります。
- バーチャルオフィス: 住所だけをレンタルするサービスです。コストを抑えられますが、許認可が必要な業種(建設業、介護事業など)では、事業実態がないと見なされ、利用が認められないケースが多いため注意が必要です。
ポイント4【設立時の財産(資本金)】:法人の「体力」はどう示す?
法人を設立する際の財産は、その法人の種類によって考え方が大きく異なります。
営利法人の場合:「資本金」
株式会社や合同会社では「資本金」が会社の「体力」を示す指標になります。会社法上は1円から設立できますが、金融機関からの融資や取引先の信用度、許認可の要件などを考慮し、3ヶ月~半年程度の運転資金を目安に設定するのが一般的です。
非営利法人の場合:「設立財産」
非営利法人の多くには「資本金」という概念がありません。その代わりに、法人形態ごとに設立時の財産に関するルールが定められています。
- 一般社団法人・NPO法人: 法律上の設立財産要件はなく、0円から設立可能です。
- 一般財団法人: 300万円以上の財産を拠出する必要があります。
- 社会福祉法人・医療法人: 明確な金額要件はありませんが、事業を行うための土地、建物、設備といった実質的な資産の確保が、設立許可を得るための大前提となります。
ポイント5【電子定款】:紙の定款なら必要な印紙代4万円が節約できる!
法人を設立する際に作成する定款を特別に「原始定款」と呼びますが、紙で作成した原始定款には、法人の種類を問わず、原則として4万円の収入印紙を貼付することが印紙税法で定められています。
しかし、この印紙税は「電子定款」というPDF形式の電磁的記録で原始定款を作成する場合には課税されません。つまり、電子定款を利用すれば、この4万円のコストを完全に節約することができるのです。
ただし、ご自身で電子定款を作成・認証手続きを行うには、ICカードリーダーライタや専用ソフトの導入など、一定の手間とコストがかかります。私たち行政書士のような定款作成に通じた専門家にご依頼いただければ、設立に関するアドバイスを受けられるだけでなく、設立費用を賢く節約するという金銭的なメリットも享受できます。
まとめ:法人の未来を決める設計図。作成は専門家にお任せください
定款は、一度作ったら終わりではありません。法人の成長に合わせて見直していく、まさに法人の「憲法」です。
この最初の設計図作りでつまずかないために、そして将来の事業展開をスムーズにするために、定款作成はぜひ専門家にご相談ください。あなたの事業ビジョンや社会貢献への想いを法的な形に落とし込み、スムーズで確実な船出をサポートします。
さらに、法人設立はゴールではなく、スタートです。設立後の各種許認可手続き、補助金・助成金の活用、日々の契約書チェックまで、事業の成長には継続的な法務サポートが不可欠です。
当事務所では、定款作成業務はもちろん、法人設立後の事業運営までを見据えた顧問契約も承っております。まずはお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。