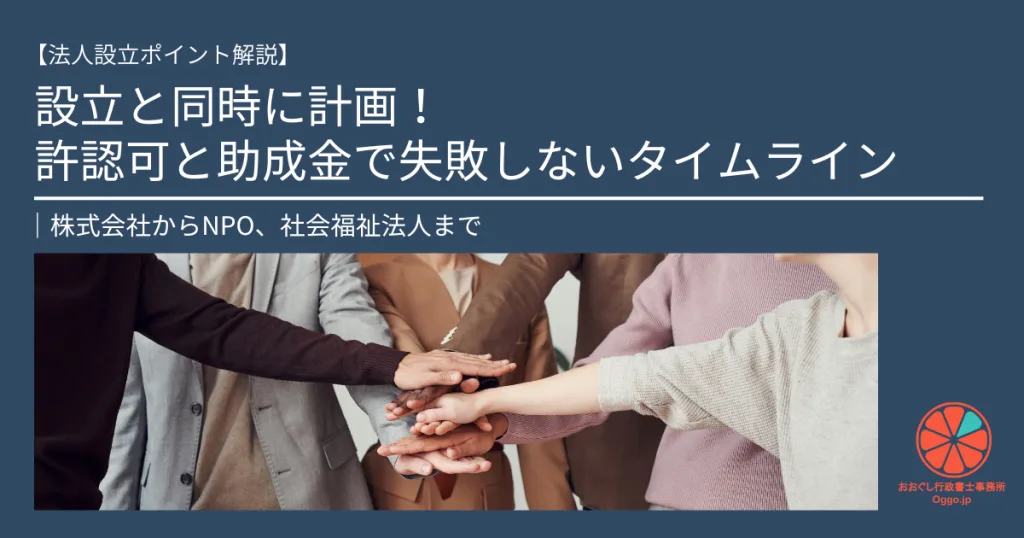【法人設立ポイント解説】資本金はいくらがベスト?事業ステージと信用力から考える最適解
はじめに:「1円で会社が作れる」は本当か?
会社設立を考えたとき、多くの方が最初に悩むのが「資本金はいくらにすればいいのか?」という問題ではないでしょうか。2006年施行の会社法によって資本金の制限がなくなり、株式会社や合同会社といった会社形態では、法律上「資本金1円」から設立できるようになりました。
しかし、本当に1円で大丈夫なのでしょうか?この問いに対し、筆者は「法律上はOKだが、事業の現実を考えるとほとんどの場合、デメリットの方が多い」と考えます。
資本金は、単なる設立要件ではありません。それは「事業の体力」であり、「社会的な信用力」の証でもあります。今回は、あなたの事業にとって最適な資本金額をどのように考えればよいか、3つの視点から解説します。
そもそも資本金の役割とは?2つの重要な側面
最適な金額を考える前に、まず資本金が持つ2つの重要な役割を理解しておきましょう。
- 会社の初期活動資金(事業の体力) 資本金は、設立した会社が事業を始め、売上が立って軌道に乗るまでの「当面の運転資金」となります。家賃、人件費、仕入れ代金など、事業を動かすには様々なお金が必要です。資本金が尽きれば、事業はすぐに立ち行かなくなります。
- 会社の対外的な信用力の指標(社会的な信用) 資本金の額は、登記情報として誰でも閲覧できます。金融機関が融資を審査する際や、新しい取引先があなたと契約を結ぶ際、この資本金の額を見て「この会社はどれくらいの体力があるのか」「事業に対する本気度はどれくらいか」を判断する一つの材料とします。資本金が極端に少ないと、信用力が低いと見なされ、融資や取引で不利になる可能性があります。
最適な資本金額を決めるための3つの視点
では、具体的にどのように金額を決めていけばよいのでしょうか。以下の3つの視点から総合的に判断することをお勧めします。
視点1:初期費用と当面の運転資金から考える
最も基本的で重要な考え方です。まずは、会社設立から事業が軌道に乗る(黒字化する)までの期間、どれくらいの費用がかかるかを計算してみましょう。
計算式: 設立にかかる諸費用 + (月々の固定費 + 変動費) × 3〜6ヶ月分
- 設立にかかる諸費用: 定款認証手数料、登録免許税など
- 月々の固定費: 事務所家賃、役員報酬、人件費、通信費など
- 変動費: 仕入れ代金、広告宣伝費、交通費など
最低でも3ヶ月、できれば半年分の運転資金を資本金として用意できれば、余裕を持ったスタートが切れるでしょう。
視点2:許認可や融資から考える
特定の事業を始めるには、行政の「許認可」が必要な場合があります。そして、その許認可の要件として、一定額以上の資本金が定められていることがあります。
- 例:建設業許可 一般建設業の許可を受けるには、「500万円以上の自己資本」が必要です。この場合、設立時の資本金を500万円以上にしておけば、スムーズに許可申請に進めます。

こちらの記事もどうぞ。資本金額だけでなく、物件契約や内装工事のタイミングでつまずかないための全体像の把握におすすめです。
また、日本政策金融公庫などから創業融資を受けたい場合も、資本金の額は重要です。自己資金(資本金)が多いほど、事業への準備と覚悟が評価され、融資審査で有利に働く傾向があります。
視点3:消費税の免税メリットとインボイス制度から考える
意外と見落としがちなのが、税金、特に消費税との関係です。
資本金1,000万円未満で法人を設立して免税事業者となることを選択すると、設立1期目と2期目の消費税の納税が免除されます(※一定の要件あり)。これは、スタートアップ期の事業者にとって非常に大きなメリットです。
もし事業規模が大きく、多額の資金が必要な場合でも、この免税メリットを享受するために、資本金をあえて「999万円」などに設定するケースは少なくありません。
【要注意】インボイス制度開始後の戦略
設立時に免税事業者となるか否かについては、2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されたことで、戦略的な判断が必要になりました。
- 免税事業者はインボイスを発行できない: 上記の免税事業者は、買手側が消費税の仕入税額控除を受けるために必要な「インボイス(適格請求書)」を発行できません。
- 取引への影響: あなたの主な取引先が法人などの課税事業者(BtoB事業)の場合、インボイスが発行できないと、取引先が税負担を強いられるため、取引を敬遠されたり、値引きを要求されたりする可能性があります。
このため、設立時には「自社の主な顧客は誰か?」という視点が重要になります。
- 顧客が一般消費者(BtoC)や免税事業者の場合: 従来通り、免税のメリットを最大限活用するのが有効です。
- 顧客が課税事業者(BtoB)の場合: 今後の取引を円滑に進めるため、設立当初からあえて「課税事業者」を選択し、インボイスを発行できるようにする戦略も検討すべきでしょう。なぜなら、課税事業者どうしの取引では、支払った消費税を「仕入税額控除」として差し引けるのに対し、免税事業者との取引では、課税事業者がその消費税分を負担することになるからです。
まとめ:資本金は事業の未来を映す鏡
ここまで見てきたように、資本金の額に「誰にとっても正しい唯一の答え」はありません。
- 事業を安定させるための運転資金はいくらか?
- 社会的な信用力をどれだけ示す必要があるか?
- 必要な許認可の要件はクリアしているか?
- 税制上のメリットを最大限に活用できているか?
これらの問いに答えながら、ご自身の事業計画に最も合った金額を設定することが重要です。資本金の額は、一度決めると変更(増資・減資)に手間と費用がかかる、非常に重要な経営判断です。
私たち行政書士は、定款作成の専門家として、お客様一人ひとりの事業計画や将来の展望をヒアリングし、適切な資本金額を見つけるお手伝いをします。
資本金のご相談はもちろん、設立手続き全体をスムーズに進めたい方は、ぜひ計画段階からお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。