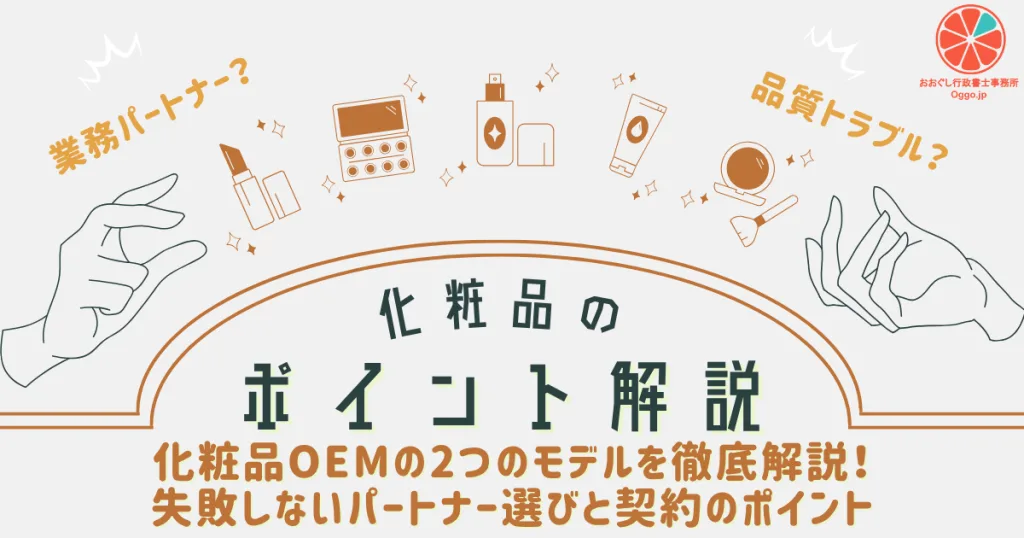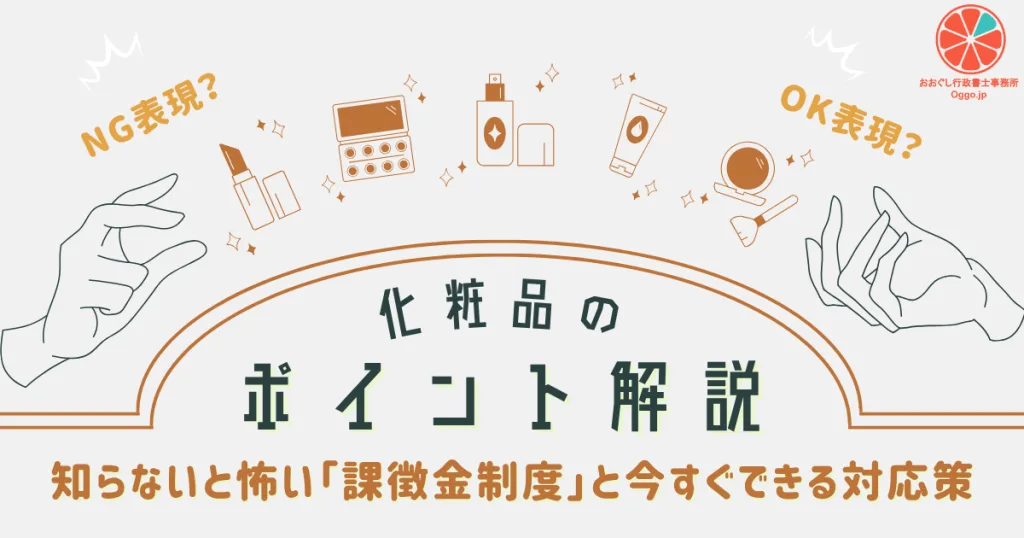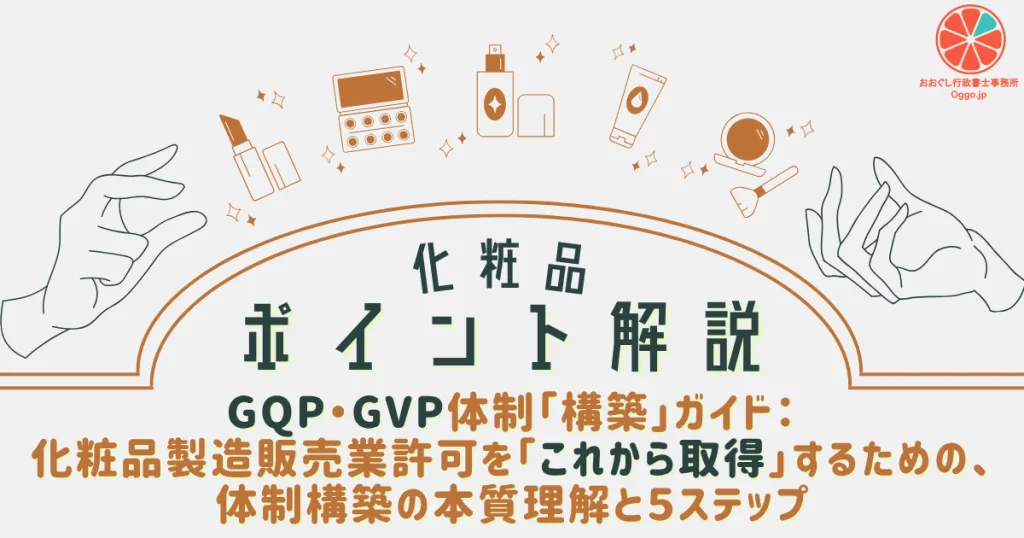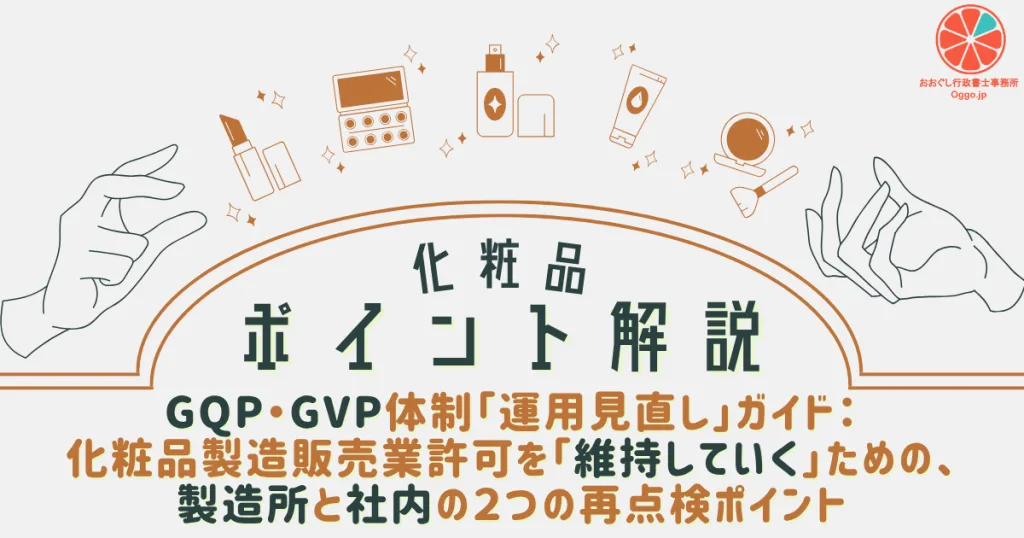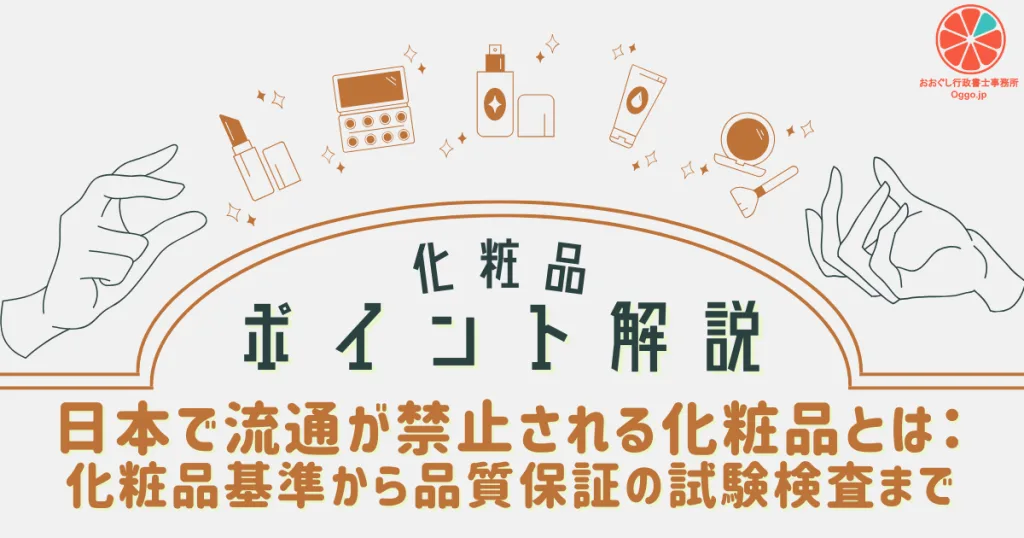化粧品製造販売業許可取得の完全ガイド – 申請から運用までのステップ –
化粧品ビジネスを始めよう、あるいは新たな化粧品を市場に送り出そうとお考えの事業者様にとって、「化粧品製造販売業許可の取得」は避けては通れない重要ステップです。この許可は、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)を遵守し、お客様に安全で信頼できる製品を届けるための基盤となります。
本記事では、化粧品製造販売業許可の全体像から、人的・物的要件、GQP/GVP体制の構築、申請手続き、そして許可取得後の運用に至るまで、事業者の皆様がスムーズに準備を進められるよう、各ステップをできるだけ網羅的に、そして分かりやすく解説します。
この記事を読めばわかること:
- 化粧品製造販売業許可の基本的な知識
- 許可取得に必要な具体的な要件(人的・物的)
- 品質管理(GQP)と製造販売後安全管理(GVP)体制のポイント
- 申請から許可取得までの流れと注意点
- 許可取得後に遵守すべきこと

化粧品ビジネスにおいては、「OEMメーカーと協力する」という選択肢も重なってきます。こちらの記事もあわせてご確認ください。
1. 化粧品製造販売業許可とは?
まず、化粧品ビジネスにおける「製造販売業許可」がどのようなものか、基本を理解しましょう。
1-1. 許可の定義と根拠法
化粧品製造販売業許可とは、化粧品を日本国内の市場に出荷し、販売するために必要な許可です。この許可は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「薬機法」といいます)第12条に基づいて与えられます。たとえ実際の製造を外部の製造業者(OEMメーカーなど)に委託する場合や、海外から化粧品を輸入して販売する場合であっても、自社の責任で化粧品を流通させたいと思うのならば、原則として自社でこの許可を取得する必要があります。
1-2. なぜ許可が必要なのか?
薬機法は、医薬品や化粧品などの品質、有効性及び安全性を確保することなどを通じて、国民の保健衛生の向上を図ることを目的としています。化粧品製造販売業者は、市場に出荷する製品の品質と安全性に対して最終的な責任を負う立場にあります。そのため、許可制度を通じて、事業者がその責任を全うできる体制(人的資源、品質管理・安全管理システムなど)を有しているかどうかが確認されるのです。
1-3. 無許可営業のリスク
化粧品製造販売業許可を受けずに化粧品を市場に出荷・販売した場合、薬機法違反となり、厳しい罰則(懲役や罰金など。薬機法第84条等)が科される可能性があります。また、行政処分として業務停止命令などを受けることもあり、企業としての社会的信用を大きく損なうことになります。

こちらの関連記事では、特に課徴金制度について詳述しています。あわせてご確認ください。
1-4. 関連する許可:化粧品製造業許可との違い
化粧品ビジネスに関連する許可には、「化粧品製造業許可」というものもあります。これらは役割が異なります。
- 化粧品製造販売業許可: 市場への製品出荷の可否を判断し、その製品の品質・安全性に最終的な責任を持つための許可です(薬機法第12条)。
- 化粧品製造業許可: 化粧品の製造(製品の包装、表示、保管のみを行う場合も含む)を行うために必要な許可です(薬機法第13条)。
自社で工場を持たずOEMメーカーに製造を委託する場合でも、市場への責任を取る者、すなわち「化粧品製造販売業許可」を持つ者は必要です。またもちろん、製造を行うOEMメーカーは「化粧品製造業許可」を取得している必要があります。
(Q&Aリンク: 化粧品を製造販売したいのですが、どのような許可が必要ですか?)
(Q&Aリンク: Q5: OEMで化粧品を製造・販売する場合も許可は必要ですか?)
2. 許可取得の全体フロー【フローチャート】
化粧品製造販売業許可を取得するまでの大まかな流れは以下の通りです。各ステップの詳細は後述します。
![化粧品許可取得の全体フロー。左から右に流れるフローチャート。左から、Step 1: 事前相談・要件確認・費用概算、Step 2: 申請書類の準備、Step 3: 許可申請、[Step 4: 書類審査・実地調査(立ち入り)、Step 5: 許可証の交付]、Step 6: 事業開始・許可取得後の遵守事項。おおぐし行政書士事務所](https://oggo.jp/wp-content/uploads/2025/06/400039263955f10ae77865ffc0b9c567.webp)
- Step 1: 事前相談・要件確認・費用概算
- まずは、事業所の所在地を管轄する都道府県の薬務主管課(薬務課、薬事課など名称は都道府県により異なります)に事前相談をすることをお勧めします。そこで、人的要件、物的要件、GQP/GVP体制について具体的なアドバイスを受けることができます。
- (Q&Aリンク:「化粧品事業を始めたいのだけれど、どのくらい費用がかかる?」)
- Step 2: 申請書類の準備
- 許可申請に必要な書類を収集し、作成します。
- 管轄の都道府県薬務主管課には適宜相談を行います。
- Step 3: 許可申請
- 準備した申請書類一式を、管轄の都道府県薬務主管課に提出します。
- 申請手数料もこの時点で納付します。
- Step 4: 書類審査・実地調査(立ち入り)
- 提出された書類に基づいて、薬務課の担当者による審査が行われます(薬機法及び関連法令への適合性確認)。
- 書類審査後、事務所や製品の保管場所などへ担当者が訪れ、実際の状況を確認する実地調査(薬機法第69条等に基づく「立ち入り」とも呼ばれます)が行われる場合があります。
- Step 5: 許可証の交付
- 書類審査及び実地調査の結果、問題がないと判断されれば、晴れて化粧品製造販売業許可証が交付されます。
- Step 6: 事業開始・許可取得後の遵守事項
- 許可取得後、いよいよ化粧品の製造販売を開始できます。ただし、後述するGQP/GVP体制の適切な運用や、変更が生じた際の届出、定期的な許可の更新など、遵守すべき事項があります。
【!】注意点: 許可申請の窓口や具体的な要件、必要書類の細部については、都道府県によって若干異なる場合があります。必ず事前に申請先の薬務主管課にご確認ください。
3. 人的要件の詳細:三役(総括・品責・安責)の資格と責務
化粧品製造販売業許可を取得し、事業を維持するためには、薬機法で定められた専門知識を持つ責任者たちを配置することが義務付けられています。ここでは、いわゆる「三役」と呼ばれる各責任者の資格要件、常勤性、兼務の可否について概説します。
3-1. 責任者の「常勤性」について
総括をはじめとする各責任者は、原則としてその事業所に「常勤」している必要があります。「常勤」とは、その事業所の営業時間中に、継続的に勤務している状態を指します。
そのため、他の会社で常勤として勤務している人を、自社の責任者として任命することはできません。また、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部改正に伴う留意事項について」の通知において、企業の管理者業務は派遣労働の対象外とされており、責任者を派遣社員で賄うことも認められません。

こちらの関連記事では、総括、品責、安責の「常勤性」や「兼務」について言及してます。あわせてご確認ください。
3-2. 総括製造販売責任者(総括)の要件と役割
- 役割: 品質・安全管理体制の最高責任者。品責・安責を監督し、品質不良や安全に関する問題が発生した際には、彼らからの報告に基づいて回収などの最終的な措置を決定し、実行を指示します。
- 資格要件(薬機法施行規則第八十五条の二第2項): 以下のいずれか一つに該当する必要があります。
- 薬剤師
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
- 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
3-3. 品質保証責任者(品責)の要件と役割
- 役割: GQP省令に基づき、市場への出荷可否の決定、製造業者との取決め管理、品質情報の処理など、品質管理業務全般を実務レベルで統括する責任者です。
- 資格要件(GQP省令第17条):
- 品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
- この「能力」とは、特定の学歴や資格が必須というわけではなく、その人物の職歴、経験、受けた教育訓練などを総合的に考慮し、製造販売業者が責任をもって「品質管理業務を任せられる」と判断できる人物を指します。
- 化粧品の販売に係る部門に属していないこと。
- 品質に関する判断が、売上や利益といった営業的な見地から影響を受けることを防ぐため、販売部門やマーケティング部門などから独立している必要があります。
- 品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
3-4. 安全管理責任者(安責)の要件と役割
- 役割: GVP省令に基づき、副作用情報などの安全管理情報の収集・検討、安全確保措置の立案・実施など、市販後の安全確保業務を実務レベルで統括する責任者です。
- 資格要件: 品責と同様に、「安全管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者」であり、「販売に係る部門に属していない」ことが求められます。
3-5. 三役の兼務について
「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律等の施行について」の通知によれば、化粧品事業においては、一定の条件を満たす場合に、総括・品責・安責の三役は一人の者が兼務することが可能です。
その「一定の条件」とは、主に「兼務する者が同一の所在地に勤務するものであって、それぞれの業務の遂行に支障を来さない等、兼務することに合理性がある範囲」とされています。
この通知は、特にスタートアップ期の企業にとって、人的リソースを効率的に配分できることからありがたいものです。ただし、実際に兼務が可能かどうかは、事業規模や業務内容の合理性を踏まえて最終的に行政が判断するため、事前確認はかならずやりましょう。
事前確認を簡単2ステップでざっくり書いておきます。必ず事前にしておくことを強くお勧めします、ほんとに。
- 候補者を選定した段階で、その方の履歴書や職務経歴書、資格証明書などを入手(この段階では写しや画像で全然OK!)
- 薬務主管課に相談・確認(FAXとか言われることあります。2025年でも…)
あやふやなときは、必ずやりましょう。「許可申請をしたら候補者の経歴では要件を満たせないと判断された」という事態は、事業計画の大幅な遅延に繋がります。でも、結構あるあるなんです。怖いですね。「薬務主管課ってどこ??」とかで後回しにしてはいけません。私の立場で言うのもなんですが、人を頼ってでもきっちり確認してください。
4. 物的要件:事務所の基準
化粧品製造販売業を行うためには、業務を適切に遂行できる事務所が必要です。
4-1. 事務所の設置
日本国内に、化粧品の製造販売に関する業務を行う主たる事務所を設置する必要があります(薬機法第12条の2第1号)。この事務所は、許可要件の一つであるGQP/GVP体制を適切に運用できる場所でなければなりません。
4-2. 必要なスペース・設備(一般的な目安)
薬機法上、事務所の広さなどに関する具体的な数値基準は設けられていませんが、一般的には以下のスペースや設備が求められます。
- 総括が業務を行うための執務スペース
- 品質管理業務及び製造販売後安全管理業務を行うために必要な書類・記録等を適切に保管するための設備(例:施錠可能な書庫やキャビネットなど)(GQP省令第16条、GVP省令第16条に関連)
- 製品の保管を行う場合は、品質に影響を与えない適切な保管設備(製造業許可の範囲となる場合があります)
賃貸物件でも問題ありませんが、事務所の構造や設備が業務に適しているか、事前に薬務主管課に相談しておくと安心です。
4-3. 事務所移転時の手続き
事務所を移転する際には、変更の日から30日以内に薬務主管課への変更届の提出が必要です(薬機法第19条第1項、薬機法施行規則第99条に基づく)。ただし、移転先が他の都道府県になる場合は、原則新たな許可申請が必要になります。つまりこの場合には事前準備の時間も考えておかないと、事業がストップしてしまいますので、注意が必要です。
(Q&Aリンク: Q10: 化粧品製造販売業許可の事務所を移転する際の手続きを教えてください。)
5. GQP・GVP体制の構築【許可の核心】
化粧品製造販売業許可を取得し、事業を継続していく上で、GQP(品質管理)とGVP(製造販売後安全管理)に基づいた体制の構築と運用は、許可の根幹をなす最も重要な要件の一つです。
GQPは市場に出荷する製品の品質を保証する仕組み、GVPは市場に出た後の製品の安全性を監視する仕組みであり、この両輪が機能することが、企業の信頼性を支えます。

これらの体制構築に関する詳細な解説や、実務における具体的なポイントについては、こちらの関連記事で詳しく説明していますので、ぜひご参照ください。
(Q&Aリンク: Q21: 許認可申請だけでなく、事業の立ち上げから全般的なコンサルティングを依頼できますか?)
6. 申請書類作成の注意点【チェックリスト】
許可申請には、様々な書類の提出が必要です。ここでは一般的な例と、その書類が何を証明・確認するためのものかを示します。
【!】重要: 以下のリストはあくまで一般的な例です。必要書類や様式は、申請する都道府県や申請内容によって異なる場合があります。必ず事前に申請先の薬務主管課に確認し、指示に従ってください。
6-1. 主な申請書類一覧(例)と法的根拠・目的
- ☐ 許可申請書(様式は各都道府県のウェブサイト等で入手)
- 根拠・目的: 薬機法第12条に基づく許可申請の本体。申請者の情報、事務所の所在地、総括の情報等を記載します。
- ☐ 登記事項証明書(法人の場合)
- 根拠・目的: 申請者の法人格及び代表者等を確認するため(商業登記法)。
- ☐ 申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)の診断書(精神機能の障害に関するもの)
- 根拠・目的: 薬機法第5条第3号ヘ(欠格事由)に該当しないことを確認するため。
- ☐ 業務分掌表、組織図
- 根拠・目的: GQP省令第3条、GVP省令第3条に規定する業務体制、特に総括、品責、安責の権限及び責任範囲が社内で明確化されているか確認するため。
- ☐ 総括の資格を証する書類(薬剤師免許証の写し、卒業証明書、単位取得証明書、実務経験証明書など)
- 根拠・目的: 薬機法施行規則第85条の2第2項に定める総括の資格要件を満たしていることを証明するため。
- ☐ 総括の雇用契約書の写しまたは雇用証明書(総括が申請者(法人の代表者など)でない場合)
- 根拠・目的: 総括が申請法人に常勤で雇用されていることを確認するため。
- ☐ GQP手順書、GVP手順書
- 根拠・目的: GQP省令及びGVP省令に基づき、適正な品質管理体制及び製造販売後安全管理体制が構築・文書化されているか確認するため。
- 【!】注意: 手順書そのものの提出が求められます。都道府県により写しの部数や様式指定の有無などが異なる場合があるため、必ず事前に確認してください。
- ☐ 事務所の平面図
- 根拠・目的: 物的要件(業務を行うスペース、書類保管場所等)が適切に確保されているか確認するため。
- ☐ その他、都道府県が指示する書類
6-2. 書類作成時のポイント
- 最新の様式を使用する: 都道府県のウェブサイト等で最新の申請様式を入手しましょう。
- 記載漏れ・誤字脱字の確認: 提出前に複数人でダブルチェックするなど、細心の注意を払いましょう。
- 添付書類の不足確認: 指示された添付書類が全て揃っているか確認しましょう。
- GQP/GVP手順書の確認: 各省令の要求事項を網羅し、自社の実態に即しているか、矛盾がないかなどを十分に確認しましょう。
- 不明点は事前に相談: 書類の書き方や必要な添付資料について不明な点があれば、遠慮なく薬務主管課に事前に相談しましょう。
6-3. 申請手数料
許可申請には手数料が必要です。手数料の額は都道府県によって異なりますので、事前に確認してください。
(Q&Aリンク: 「化粧品事業を始めたいのだけれど、どのくらい費用がかかる?」)
6-4. 申請窓口
申請書類の提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の薬務主管課です。
7. 許可取得後の運用と更新
許可証が交付された後も、気を緩めることなく適切な事業運営が求められます。
7-1. 遵守すべき主な事項
- GQP/GVP体制の継続的な運用と改善: 定期的な自己点検や教育訓練を通じて、体制の維持・向上に努めましょう(GQP省令、GVP省令)。
- 手順書の定期的な見直しと改訂: 法改正や業務内容の変更に合わせて、手順書を最新の状態に保ちましょう。
- 品質記録、安全管理記録の適切な作成と保管: 全ての業務は記録に基づき行われ、その記録は定められた期間、適切に保管する必要があります(GQP省令第16条、GVP省令第16条)。
- 変更が生じた場合の変更届の提出: 総括の変更、事務所の移転、法人の名称や役員の変更など、届出事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に薬務主管課に変更届を提出する必要があります(薬機法第19条第1項、薬機法施行規則第99条に基づく)。
- 行政による立入検査(立ち入り)への対応: 定期的または随時に、薬務主管課による立入検査(立ち入り)が行われることがあります(薬機法第69条等)。日頃から法令遵守の意識を持ち、適切に対応できるように準備しておきましょう。

こちらの関連記事では、記録の保管について言及してます。あわせてご確認ください。
7-2. 許可の有効期間と更新手続き
化粧品製造販売業許可には有効期間があり、通常は5年です。引き続き事業を行う場合は、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります(薬機法第12条第4項、施行令第3条)。更新時にも、GQP/GVP体制が適切に運用されているかなどが確認されます。
8. まとめ
化粧品製造販売業許可の取得は、安全で信頼される化粧品を市場に提供するための、長く重要な道のりの第一歩に過ぎません。本記事で解説した通り、人的要件、物的要件、そしてGQP・GVP体制の構築と適切な運用は、許可を取得するためだけでなく、その許可を維持し、事業を継続していく上で不可欠なものです。
忘れてはならないのは、この許可は「これから許可を返上するまでの間、許可要件を満たし続けられるという見込みがある」として与えられるものであり、ゴールではないということです。万が一、許可要件を満たさなくなった場合には、許可が取り消されることもあります。つまり、許可取得はビジネスのスタート地点であり、そこから真摯な事業運営が求められます。
化粧品を含むヘルスケア製品は、直接人の肌に触れ、心身に影響を与えるものです。だからこそ、このビジネスには大きな責任と覚悟が求められます。しかし、それと同時に、人々の美と健康に貢献し、多くの笑顔を届けられる、非常にやりがいのある事業でもあります。
申請手続きは複雑な部分もあり、継続的な法令遵守も容易ではないかもしれませんが、計画的な準備と日々の努力、そして必要に応じた専門家(行政書士など)のサポートを活用することで、道は拓けます。
(Q&Aリンク: Q17: 相談したいのですが、費用はかかりますか?)
(Q&Aリンク: Q22: 薬事コンサルティングを行う行政書士は他にもいますが、どのように選べばよいですか?)
本記事が、化粧品ビジネスという魅力的な世界へ踏み出す皆様の確かな一歩を後押しし、その素晴らしい事業を力強く展開していくための一助となれば、これほどうれしいことはありません。さあ、一緒に頑張っていきましょう!
【参考文献・情報源】
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
- 化粧品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(GQP省令)
- 化粧品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP省令)
- (各都道府県)薬務課発行「化粧品製造販売業許可申請の手引き」等
- 厚生労働省ウェブサイト
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ウェブサイト
【免責事項】 本記事は、化粧品製造販売業許可に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の案件に対する法的アドバイスを提供するものではありません。許可申請にあたっては、必ず最新の法令・通知等をご確認の上、管轄の都道府県薬務主管課または専門家にご相談ください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。