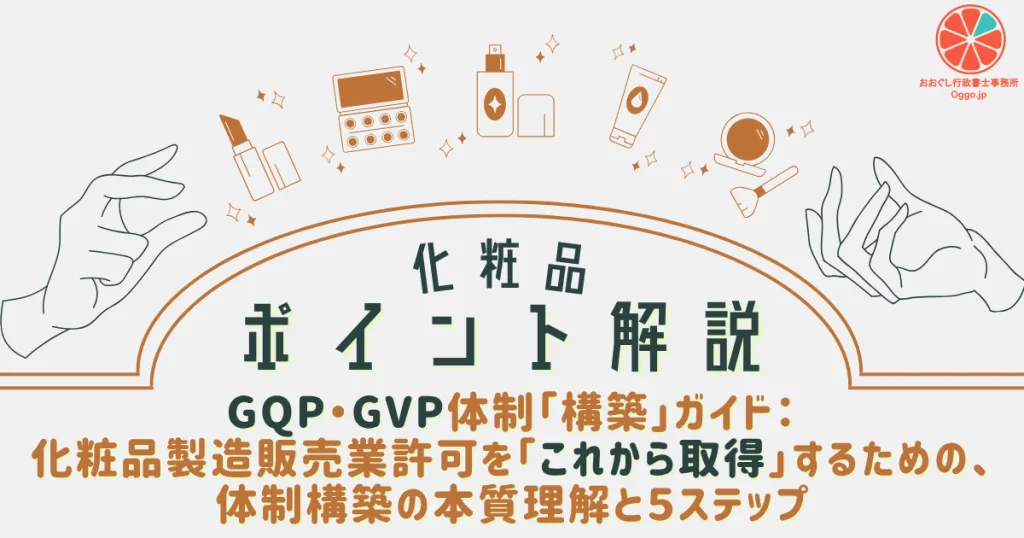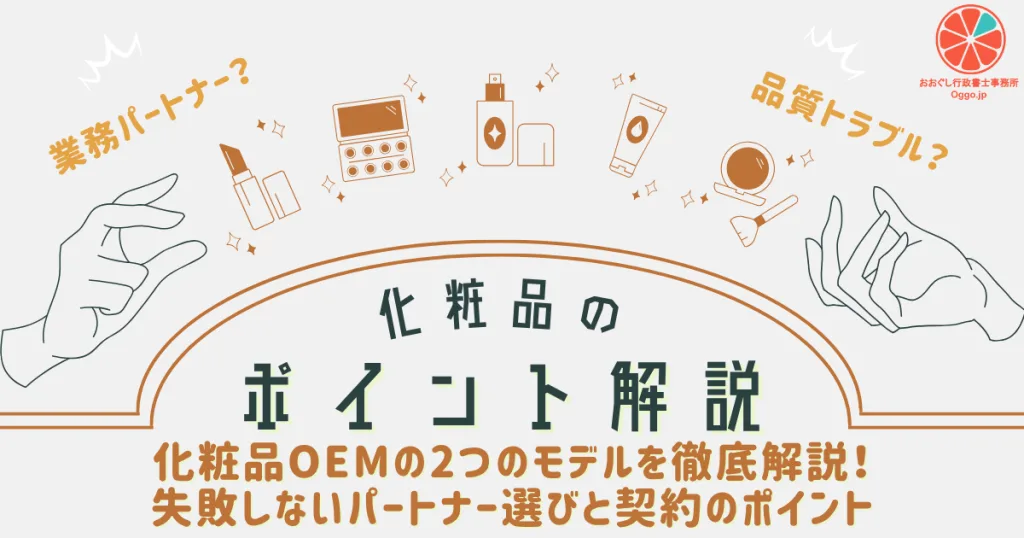GQP・GVP体制「運用見直し」ガイド:化粧品製造販売業許可を「維持していく」ための、製造所と社内の2つの再点検ポイント
すでに化粧品・医薬部外品の製造販売業許可を取得し、GQP・GVP体制を運用されているご担当者様方は、このような課題感をお持ちではないでしょうか。
- 「委託先(OEM)製造所のGMP管理は、今のままで十分だろうか」
- 「社内の内部監査や手順書が、形骸化していないか不安がある」
- 「2025年中に施行が見込まれる改正薬機法(※)に向け、GQP/GVP/GMP体制全体を点検したい」(※※これまでGQP省令で定められていた、品質保証責任者による製造所の管理監督(GMP遵守状況の確認等)に関する責務が、薬機法本体に規定され、法律上の直接的な義務となります)
化粧品・医薬部外品の品質と安全を守る仕組み(QMS)は、一度構築して終わりではありません。特に「化粧品GMP」との連携、つまり製造所の管理監督は、改正薬機法において最も厳しく見られるポイントの一つです。
この記事では、既存のGQP/GVP体制が「実効性」を保っているか確認するため、「製造所管理(GMP)」と「社内QMS運用」の2つの側面から再点検ポイントを、法的根拠と共に解説します。

GQP、GVP、化粧品GMPの基本的な定義や、新規で体制を構築する手順については、こちらのポイント解説記事をご覧ください。
■ なぜ今、「実効性のある」体制見直しが重要なのか?
GQP省令に基づき、製造販売業者は委託先製造所の管理監督を行う必要があります。
従来、これはGQP省令(品質管理の基準に関する省令)上の要求でしたが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和五年法律第三十七号)が成立し、関連規定が2025年中に施行される見込みです。この改正により、品質保証責任者の設置とその責務(製造所の管理監督を含む)が、ついに薬機法本体に規定され、「法律上」の直接的な義務となります(改正後薬機法第十七条等)。
これは、「製造委託先への丸投げ」は許されず、製造販売業者(GQP)が品質に対して最終的な責任を持つという姿勢を、国がより強く求めていることの表れです。
形式的な手順書や監査だけでは、今後の要求水準を満たせない可能性があります。今こそ、自社の体制が「実効性」をもって機能しているか、見直す必要があります。
■ 再点検ポイント1:製造所管理(GQP-GMP連携)の実効性
GQP体制の核となるのが、製造所(GMP)との連携です。
1-1.「取決め書」は形式的になっていないか?
製造業者との間で業務範囲や手順、責任の所在を明確にする「取決め書」は、GQP省令で締結が義務付けられています。
チェックポイント:
- 「逸脱」や「仕様変更」(軽微変更含む)が発生した際、製造所からGQP部門へ報告・承認を求めるフローが明確かつ現実的ですか?(GQP省令 第七条第一項第一号、第三号の準用)
- 製造所に対する定期監査・臨時監査の権限と手順が明記されていますか?(GQP省令 第七条第一項第二号の準用)
- (最後に更新したのはいつですか? 改正法の趣旨を反映できていますか?)
1-2.「委託先監査(GMP監査)」は形骸化していないか?
製造販売業者は、製造業者の製造・品質管理体制が適切であることを定期的に確認する義務があります。この確認は通常、監査によって行われます。
チェックポイント:
- 毎年、同じチェックリストを使い、指摘事項のない「無事終了」を目的とした監査になっていませんか?(GQP省令 第七条第一項第二号の準用)
- 監査で発見された事項(指摘事項)に対する、製造所からの是正措置(CAPA)の報告を確実に受領し、その有効性をGQP部門が評価・確認していますか?
再点検ポイント2:社内QMS運用(GQP-GVP連携)の実効性
製造所管理が適切でも、社内の運用が形骸化していては「実効性のあるQMS」とは言えません。
2-1.「自己点検(内部監査)」は発見の場として機能しているか?
自社のGQP業務が手順書通りに実施され、有効に機能しているかを確認する「自己点検」は、GQP省令で義務付けられています。
チェックポイント:
- 自己点検(内部監査)が「不適合を罰する場」ではなく、改善の種を「発見する場」として機能していますか?(GQP省令 第十四条の準用)
- 監査担当者が固定化され、客観的な視点が失われていませんか?
- 手順書が、現場の実務担当者(例:品質保証担当者)にとって理解できる内容になっていますか?(手順書と実務が乖離していませんか?)
2-2.「GVP(安全)情報」はGMP改善に活かされているか?
顧客から寄せられる情報の中には、製品の品質改善に繋がる貴重なヒントが隠されています。GVPとGQPの連携は、法的に見ても極めて重要です。
チェックポイント:
- GVP部門に寄せられた顧客からのクレーム(例:「いつもと匂いが違う」「異物が入っていた」など)は、単なる「安全性の問題なし」で処理されていませんか?これらはGVP省令で定められた「品質に関する安全管理情報」です。(GVP省令 第二条第一項)
- それらの「品質に関する情報」は、GQP部門を通じて製造所に速やかにフィードバックされ、製造工程(GMP)の原因究明や再発防止に活用されていますか?(GQP省令 第十一条、GVP省令 第十三条の二の準用)
- 総括製造販売責任者が、GQPとGVP両部門からの報告に基づき、市場出荷の可否を総合的に判断できる体制が整っていますか?(薬機法 第十七条第一項)
化粧品OEM契約における「製造販売業者」の責任については、こちらの記事もご参照ください。
■ まとめ
GQP/GVP体制と化粧品GMPの連携見直し、そしてQMS運用の実効性確保は、改正薬機法への対応はもちろん、自社ブランドの品質と安全を守るための重要な経営課題です。
おおぐし行政書士事務所では、改正薬機法に対応したGQP手順書の見直し、実効性のある「取決め書」の作成支援、委託先監査(GMP監査)や自己点検(内部監査)の実施支援など、実務に即したサポートを提供しております。
「自社の体制が十分か、専門家の視点で確認してほしい」 「改正法に対応した手順書や取決め書に更新したい」
このようなご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。