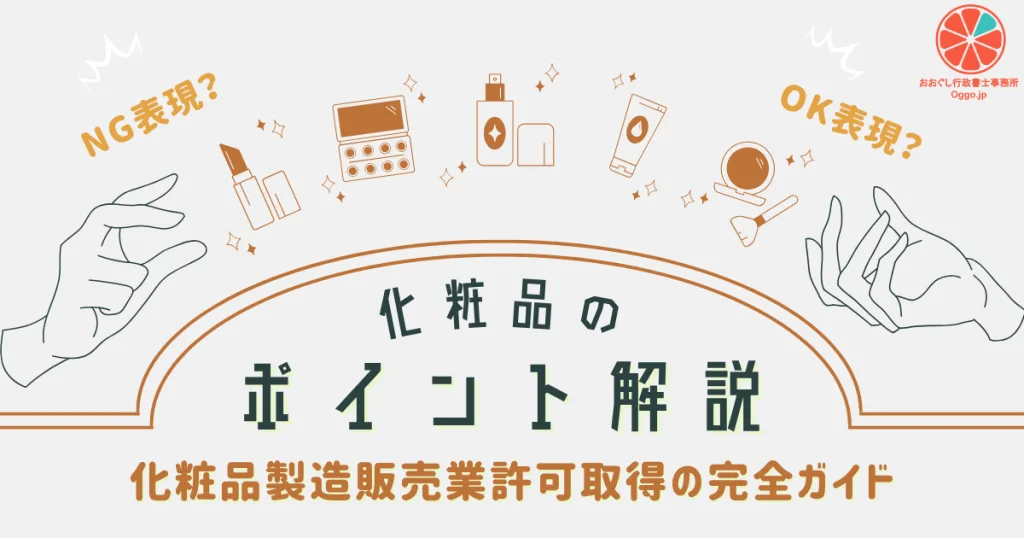薬機法の責任者への「直接雇用」と 「常勤性」の要求は、なぜ?
責任者の「直接雇用」「常勤性」は当たり前?その法的根拠を深掘り
行政書士として薬機法関連の許認可業務に携わっていると、様々な「要件」に直面します。その中でも、事業者様に設置が義務付けられている各種責任者の「常勤性」は、いわば“当たり前”の要件として認識されており、その根拠が改めて問われることはほとんどありません。しかし、「なぜ当たり前なのだろう?」とふと気になり、その法的根拠を改めて深掘りしてみることにしました。
今回の忘備録は、化粧品、医薬部外品の事業者と各責任者との関係性における「直接雇用」「常勤性」「専従性」という3つの要点について、なぜ、またどのように求められるのかについて調べたものを記したものです。
第1章:直接雇用 - 責任の所在を明確にするための大原則
化粧品・医薬部外品の製造販売業・製造業許可の根幹をなすのが、総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者、責任技術者(以下、総括等)の設置義務です。そして、これらの責任者は事業者による「直接雇用(または法人の常勤役員であること)」が原則とされています。その根拠は、まず薬機法等の条文そのものから読み解くことができます。

こちらの関連記事では、総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者、責任技術者の設置義務について詳述しています。
1-1. 薬機法等が求める「業者に置く」こと
各責任者の設置義務を定めた法令の条文には、繰り返し「業者に置かなければならない」と規定されています。
- 薬機法第17条第2項は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者に「医薬品等総括製造販売責任者」を置くことを義務付けています
- 薬機法第17条第10項は、医薬部外品又は化粧品の製造業者に製造所ごとに「責任技術者」を置くことを義務付けています
- 医薬品の品質管理に関するGQP省令(品質管理基準)第3条第1項は、医薬品の製造販売業者に「品質保証責任者」を置くことを義務付けています
- 医薬品の製造販売後安全管理に関するGVP省令(製造販売後安全管理基準)第2条第2項は、第一種製造販売業者に「安全管理責任者」を置くことを義務付けています
この「業者に置く」という要件は、単に名義上の登録を求めるものではないことは、当然の話だろうと考えます。さらに、続く1-2でも裏付け情報を示します。
薬機法や関連省令等での明確な文言は今のところ見つけられていませんが、まずまず「直接雇用」の根拠と言っても論理の飛躍はないだろうと私は解釈しています。
国民の保健衛生に直結する業務であるからこそ、責任の所在が曖昧になる派遣等の間接的な雇用形態は、法の趣旨にそぐわないものですからね。
1-2. 裏付け:「労働者派遣の例外規定」
①各責任者は派遣労働者ではダメという解釈
この解釈の裏付けとして、平成11年11月30日付の三局長通知(健政発第1290号等)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部改正に伴う留意事項について」が存在します。
この通知では、労働者派遣が原則自由化された際、例外的に派遣が認められない業務が定められ、その中に以下の業務が明確に含まれています。
(4) 薬事法(昭和35年法律第145号)第9条...及び同法第15条...に規定する管理業務
(5) 薬事法第17条に規定する医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造の責任技術者の業務
この通知は平成17年の薬事法改正(製販分離)以前のもので、未だ廃止されたという話は聞きません。
当時の責任技術者は現在より広範な責任を担っており、その業務は現在の三役(総括・品責・安責)の業務に相当するものも含まれていました。したがって、これら三役も当然に適用除外の対象、すなわち派遣労働者による責任技術者の業務及び三役(総括・品責・安責)の業務は認められていないと解釈できるでしょう。
②なぜ派遣ではダメなのか? - 指揮命令権とガバナンスの論点
前述の通知が労働者派遣を禁止する理由として「保健衛生上支障を生ずるおそれがないように管理するものであることから」と明記している点は重要です。
労働者派遣という雇用形態では、雇用主(派遣元)と業務の指揮命令者(派遣先である事業者)が分離してしまいます。この分離を認めてしまうと、特に重大な品質問題や安全上の懸念が発生した際に、迅速かつ的確な意思決定を妨げ、事業者のガバナンスが十全に及ばないリスクを生じさせるでしょう。このような「ガバナンスの希薄化」こそが、行政が懸念する「保健衛生上の支障」に直結すると考えるのでしょう。
つまり、前述の通知(労働者派遣の禁止)は、「保健衛生上重要な責任者として位置づけられているこれらの責任者については、事業者が直接の管理監督下に置き、その業務遂行に対して完全な責任を負うべきである」ということです。薬機法、同施行規則、GQP省令、GVP省令等の各条文の示すところから見ても納得がいきます。そしてこのことに鑑みれば、事業者からの具体的な指揮命令が及ばない業務委託契約(準委任契約)もまた、同様に認められないと解釈するのが妥当だろうなーとも考えます。
③直接雇用の必要性ー労働者派遣の例外規定から
というわけで、先ほど書いた「保健衛生上重要な責任者として位置づけられているこれらの責任者については、事業者が直接の管理監督下に置き、その業務遂行に対して完全な責任を負うべきである」に戻りますが、まあこれは普通に読んで、「事業者との直接の雇用契約」または「事業者の常勤役員であること」という形態を想定しているといっていいでしょう。
1-3. 結論「直接雇用は要件」
以上のことから、各責任者は事業者から直接雇用されることが必須条件と言ってもよいだろうと結論付けます。
第2章:常勤性 - 明文なき「事実上の要件」
次に「常勤性」です。実は、薬機法および関連省令のどこにも「常勤でなければならない」という明確な文言はありません。にもかかわらず、なぜ“当たり前”の要件とされているのでしょうか。その答えは、行政の許可審査実務にあります。
2-1. 法令上の明文規定の不在
薬機法、同施行規則、GQP省令、GVP省令の各条文を精査しても、総括、品責、安責、責任技術者のいずれについても、その要件として「常勤」という文言は直接的には規定されていない。法令は、資格要件(例:薬剤師であること)や、遵守すべき事項、業務内容を定めるに留まっています。
だとすると、非常勤での就任もできちゃうんじゃない…と思えるところですが、実態は異なります。
2-2. 都道府県の行政実務から浮かび上がる「実質的な常勤性」の要請
「常勤性」の要件は、法令の明文ではなく、許可権者である都道府県知事による行政解釈と、許可申請時の添付書類を通じた審査基準(運用)によって実質的に担保されているようです。各都道府県の薬務課が公開する許可申請の手引きや様式例から明確に読み取れますので、いくつか例を挙げてみましょう。
- 東京都福祉保健局は、医薬品製造販売業の許可申請の添付書類として、「総括製造販売責任者の雇用契約書の写し又は雇用若しくは使用関係を証する書類」を要求している。さらに、その書類には「休日は具体的に記入してください。(例:土曜・日曜・祝日※「会社の定める日」など客観的に勤務状況がわからない記載は不可。)」との注記があり、勤務実態を客観的かつ厳格に確認する姿勢を示している。
- 神奈川県も、医療機器修理業の許可申請において同様に「責任技術者の雇用証書」を求め、業務内容、勤務時間、休日の記載を要求しており、これは他の業許可においても準用される考え方である。
- 愛知県は、許可申請手引きの添付書類サンプルとして「別紙2 雇用証書(例文)」を公開しており、ここでも勤務時間や休日を明記する運用が前提となっていることがわかる。
これらは申請書類上の要求ですが、実際の審査においても、各責任者の勤務時間は、原則として事業所の営業時間中、常に勤務していることが前提とされています。比較的短時間勤務が認められるか否かは、個別の事情に応じて都道府県の判断が分かれるのが実情です。
では、なぜ法令に明記がないにもかかわらず、行政はこれほどまでに「常勤性」を重視するのでしょうか。その理由は、薬機法の目的である「国民の保健衛生の向上」から考えてみると、見えてきます。薬機法は、事業者が製品の品質と安全を確保するための体制を適切に構築・維持することを求めています。その体制の中核を担うべき責任者が、週に数日・数時間しか勤務しない非常勤であった場合、日常的に発生しうる品質情報や安全上の懸念への迅速な対応、関連部門との連携、体制全体の監督といった重責を十全に果たすことは物理的に不可能です。
例えば、製造現場で急な品質トラブルが発生した際や、消費者から重篤な副作用情報が寄せられた際に、責任者が不在であれば、的確な指示や判断が遅れ、国民の健康に重大なリスクをもたらしかねません。
したがって、都道府県は、法の趣旨を実質的に満たすためには、責任者が「常時」その事業所に勤務し、責任を全うできる状態にあること、すなわち「常勤性」が必須であると判断しているのです。
2-3. 「常勤」の定義と解釈
そもそも、常勤とはなにか、という話になりますが、やっぱり薬機法関連法規には「常勤」や「常勤性」の定義はなされていないので、また悩ましい話となります。
そもそも「常勤」という言葉に、あらゆる場面で通用する単一の法的定義は存在しません。この言葉の意味は、それが使われる法律や業界の文脈によって大きく異なるのです。以下に例を挙げますが、行政実務における「常勤」とは、必ずしも「正社員」「パートタイム従業員」「契約社員」「嘱託社員」といった特定の雇用形態を指すものではないようです。重要なのは勤務実態であり、一般的には「当該事業所の就業規則等で定められた常勤職員(フルタイム従業員)の所定労働時間、勤務する日数のすべてを勤務する者」というイメージなのかなと思います。
- 医療分野: 厚生労働省医政局長が発出した通知「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」(令和5年6月10日医政発0610第11号)によれば、「常勤医師」とは、原則としてその病院が定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者を指すとされています。ただし、常勤換算を行う際などには、常勤の勤務時間が週32時間未満の場合は32時間を基準として計算するなど、実務上「週32時間」が一つの重要な目安として扱われています。
- 福祉・介護分野: 厚生省(当時)が発出した通知「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)において、「常勤」とは当該事業所の就業規則等で定められた常勤従業者の勤務時間数に達していることを指し、その時間数が週32時間を下回る場合は、週32時間を基本とする、と示されています。
- 社会保険制度: 健康保険法や厚生年金保険法に基づく解釈では、週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常の労働者の「4分の3以上」というのが加入の一つの基準です。しかし、平成28年(2016年)10月以降、短時間労働者への適用は段階的に拡大されており、この基準を満たさなくても、「週の所定労働時間が20時間以上」「月額賃金が8.8万円以上」などの要件を満たせば適用対象となります。
- 建設業界: 経営業務の管理責任者や専任技術者には、「名義貸し」の防止などを目的に、特に厳格な常勤性が求められます。国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン(最終改正令和7年2月1日国不建第161号)」においては、「役員のうち常勤であるもの」が、原則として本社や本店等において、休日を除いて毎日所定の時間その職務に従事している状態を指す旨示されています。
これらの行政実務は、許可権者である都道府県が、薬機法の目的を達成するためには各責任者の常勤性が不可欠であると解釈していることを示してます。薬機法は、事業者が製品の品質と安全を確保するための体制を適切に構築し、維持することを求めています。その体制の中核を担うべき責任者が、例えば週に1日や数時間しか勤務しない非常勤の形態であった場合、日常的に発生しうる品質情報や安全上の懸念への迅速な対応、関連部門との連携、体制全体の監督・統括といった重責を十全に果たすことは物理的に不可能でしょう。
したがって、都道府県は、法の趣旨を実質的に満たすためには、責任者が「常時」その事業所に勤務し、責任を全うできる状態にあること、すなわち「常勤性」が必須であると判断しているのでしょう。責任者が非常勤であった場合、例えば、製造現場で急な品質トラブルが発生した際や、消費者から重篤な副作用情報が寄せられた際に、即座に状況を把握し、的確な指示を出すことが困難になります。このような対応の遅れが、国民の保健衛生に重大なリスクをもたらしかねません。だからこそ、許可権者である行政は、申請の段階で実質的な常勤性を厳しく審査しているのです。そして、この行政解釈を担保するための具体的な手段として、許可申請時に勤務実態が明記された雇用契約書等の提出を義務付け、審査の段階でその妥当性を判断するという運用が全国的に定着しているのだと推察します。
この運用は、私自身の経験とも合致します。複数の行政書士事務所さんを含む薬事支援系のウェブサイト上の情報でも「常勤での配置が必要」「常勤であることが必須」と頻繁にかかれているところからも、業界の当たり前化してるのかもしれません。
2-4. 結論「常勤性は事実上の要件」
以上のことから、各責任者は常勤性がある程度の拘束力を持って求められると言ってもよいだろうと結論付けます。ただ、私の経験上、結構この点については柔軟に対応いただけるようになってきてるんですよね。まずはお問い合わせいただきたいところです。
なお、許可申請時には責任者の現住所も記載事項となるため、事業所に日常的に通勤可能な物理的距離に居住していることも、常勤性を証明する上での間接的な要素として考慮される場合があることを留意しておく必要があります。
第3章:専従性 - 独立性と兼務のバランス
責任者は、他の業務と兼務せず、その業務に専従する必要があるのでしょうか。結論から言うと、「一定の条件下で兼務は可能」です。
3-1. 販売部門からの独立性の確保
まず守るべき大原則は、品質管理・安全管理の独立性です。GQP省令・GVP省令では、品質保証責任者と安全管理責任者は、それぞれ「医薬品等の販売に係る部門に属する者でないこと」と規定されています。これは、営業部門の利益追求によって、品質や安全性に関する客観的な判断が歪められることを防ぐための重要な規定です。
3-2. 合理的な範囲で認められる兼務
この独立性を確保し、各業務の責任を全うできる合理的な範囲であれば、責任者間の兼務は認められています。
| 兼務パターン | 可否 | 根拠・留意点 |
|---|---|---|
| 総括 ⇔ 品責 ⇔ 安責 | 可 | いわゆる「三役」の兼務。資格要件を満たし、業務に支障がなければ1名で三役を兼務可能。 |
| 三役 ⇔ 責任技術者 | 可 | 製造販売業者の主たる事務所と製造所が同一施設内にあるなど、業務に支障がないと認められる場合。 |
| 三役 ⇔ 販売部門の者 | 不可 | GQP/GVP省令で禁止。 |
※上記は一般的なケースであり、具体的な兼務の可否は、事業所の規模、業務量、管理体制などを総合的に勘案し、許可権者である都道府県が判断します。
【補足】混同しやすいポイント - 「総括等」と「責任役員」は別人です
最後に、実務上よく混同されがちな点について補足します。「総括製造販売責任者」と「薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)」は、薬機法上、明確に異なる役割を持つ別の存在です。
なぜ役員でも「総括等」になれるのか?
「直接雇用」の原則は、役員が総括等に就任することを妨げません。なぜなら、常勤役員は、指揮命令・監督関係の明確性や責任の所在という点で、直接雇用の趣旨を従業員以上に満たす存在だからです。役員が就任する場合は、雇用契約書に代わり、「登記事項証明書」や、その役員を責任者に任命した「取締役会議事録」などで事業者との関係性を証明します。
「総括等」と「責任役員」の役割の違い
| 総括製造販売責任者 等 | 薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員) | |
|---|---|---|
| 役割 | 現場の実務責任者 | 経営レベルの監督責任者 |
| 責務 | 品質管理や安全管理の実務を統括・実行する。現場の専門家として経営陣に意見具申する。 | 会社全体の法令遵守体制を構築・運用することに責任を負う。総括等からの意見具申を尊重し、経営判断を下す。 |
| 根拠 | 薬機法第17条、GQP/GVP省令など | 令和元年改正薬機法で導入 |
| 該当者 | 資格要件を満たす者 | 会社を代表する取締役や薬事業務担当取締役など(資格要件なし) |
第4章:各責任者における雇用要件の個別分析
これまでを踏まえ、本章では4つの責任者それぞれについて、雇用形態に関する要件を個別に整理し、結論を導き出す。
4-1. 総括製造販売責任者
- 設置根拠: 薬機法 第17条第1項。
- 直接雇用: 必須。労働者派遣は平成11年通知により明確に禁止されている(第1章の結論)。
- 常勤性: 実質的に必須。許可申請時に雇用契約書等でフルタイム勤務であることが確認される(第2章の結論)。
- 兼務:
- 品責、安責との三役兼務は、業務に支障がなく合理性が認められる範囲で可能である。
- 責任技術者との兼務も、製造所が総括の主たる業務地(製造販売業者の事務所)と同一施設内にあるなど、実地管理が可能な条件下で認められる。
- ただし、販売部門の役職との兼務は利益相反の観点から認められない。
4-2. 品質保証責任者
- 設置根拠: GQP省令第3条第1項(化粧品・医薬部外品はGQP省令第19条により準用)。
- 直接雇用: 必須。総括が監督する品質管理業務の中核を担うため、平成11年通知の趣旨が同様に適用される(第1章の結論)。
- 常勤性: 実質的に必須。日常的な品質管理業務を統括するため、常時事業所に在籍していることが求められる(第2章の結論)。
- 兼務:
- 総括、安責との兼務は可能。
- 責任技術者との兼務も、製造所が主たる事務所と同一施設内にある等の条件を満たせば可能である。
- GQP省令第17条第2号により「販売に係る部門に属する者でないこと」が明記されており、販売部門との兼務は明確に禁止されている
4-3. 安全管理責任者
- 設置根拠: GVP省令 第2条第2項
- 直接雇用: 必須。品質保証責任者と同様、平成11年通知の趣旨が適用される(第1章の結論)。
- 常勤性: 実質的に必須。市販後の安全情報の収集・評価・措置といった機動性が求められる業務を統括するため、常勤性が不可欠である(第2章の結論)。
- 兼務:
- 総括、品責との兼務は可能。
- 責任技術者との兼務に関する明確な規定は見当たらないが、業務に支障がなく、利益相反が生じない等の合理性が認められれば可能と解される。
- GVP省令第13条第2項第2号により「販売に係る部門に属する者でないこと」が明記されており、販売部門との兼務は明確に禁止されている。
4-4. 責任技術者
- 設置根拠: 薬機法 第17条第10項。
- 直接雇用: 必須。平成11年通知により労働者派遣が明確に禁止されている(第1章の結論)。
- 常勤性: 実質的に必須。薬機法第17条第10項の「製造を実地に管理させるため」という文言は、責任技術者が常に製造現場に存在し、直接監督することを要請していると解釈される。したがって、4つの責任者の中でも特に常勤性の要請が強い。
- 兼務:
- 自社内の複数製造所の責任技術者の兼務は、十分な管理が行えることを条件に可能である。
- 総括、品責との兼務も、製造所が主たる事務所と同一施設内にあるなど、実地管理の要件が満たされる場合に可能である。
まとめ
責任者の「直接雇用」と「常勤性」は、単なる慣例ではなく、製品の品質と安全性を最終的に事業者が担保するための、薬機法の根幹に関わる要請です。その根拠は、法令の条文解釈、行政通知、そして許可行政の実務運用の中に見出すことができたように思います。今後も、こうした“当たり前”の背景にある法的論理を意識しながら、業務に取り組んでいきたいと思います。
※本コラムは、個人的な見解を述べたものに過ぎず、この記載によって何らかの損害が生じたとしても一切の責任は持ちません。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。