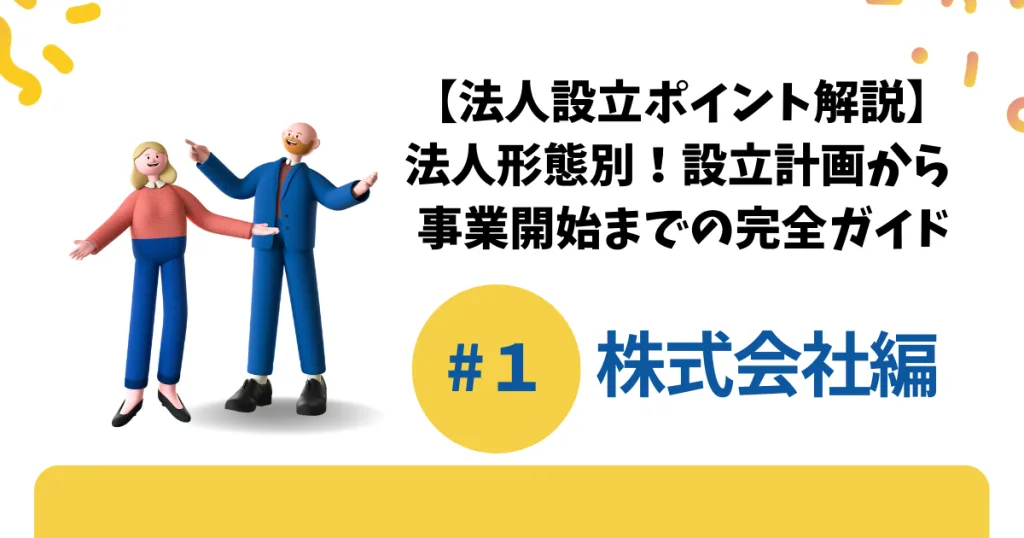人を雇う? 行政書士を顧問にする? 顧問行政書士がもたらす経営価値とコスト低減
はじめに:会社の成長と人手の悩ましい関係
スタートアップ、中小企業、そして大企業の新規事業部門まで、企業の成長ステージを問わず、多くの経営者が同じ壁にぶつかります。それは、「事業を大きくしたいが、法務や総務などの管理業務が追いつかない」というジレンマです。特に、ヘルスケアや大学発ベンチャーのように高度な専門性が求められる分野では、複雑な法律や行政手続きが成長の足かせとなることさえあります。
かといって、管理部門のスタッフをすぐに一人雇うのは本当に賢明な判断でしょうか。人件費は固定費として重くのしかかり、企業の財務体力を着実に削っていきます。
「事業の成長スピードを落とさずに、管理体制を強化する、もっと賢い方法はないだろうか?」
この記事は、そんな経営者のためのものです。答えは、行政書士を単なる手続きの代行者ではなく、「経営戦略のパートナー」として顧問に迎えること。これは、新しい社員を一人雇う数分の一のコストで、法務・管理部門のプロフェッショナルをチームに加えることに他なりません。単なるコスト削減の話ではないのです。会社の成長を加速させ、見えないリスクから会社を守る、きわめて合理的な経営判断としての「顧問行政書士」の価値を解き明かします。
第1章:単なる「手続き代行」ではない。顧問行政書士がもたらす4つの経営価値
多くの方が、行政書士の仕事を「許認可を取ってくれる専門家」というイメージで捉えているかもしれません。しかし、顧問契約を結ぶことで、その価値はまったく新しい次元に変わります。顧問行政書士は、会社の成長を隣で支え続ける「社外の戦略パートナー」となるのです。
1. いつでも相談できる「法務の壁打ち相手」がいる安心感
日々の業務では、「この新規事業、法的に問題ないか?」「行政から届いたこの通知、どう対応すべきか?」といった判断に迷う場面が絶えません。そんな時、気軽に相談できる専門家がいることは、経営者にとって何よりの精神的な支えとなります。問題を後回しにして大きなトラブルに発展する前に、いつでも専門家の視点から客観的なアドバイスを得られます。
2. 問題が起きる前に手を打つ「予防法務」というリスク管理
デキる経営者は、問題が起きてから対処するのではなく、問題が起きない仕組みを作ります。顧問行政書士は、まさにその「予防法務」のプロです。行政の監査や立ち入り検査といった万が一の事態に備え、日頃から法令を遵守したクリーンな経営体制の構築をサポートします。この地道な取り組みが、将来の行政処分や訴訟といった、事業の存続を揺るがしかねないリスクを未然に防ぐのです。
3. 知らないでは済まされない「法改正」の波を乗りこなす
法律や条例は、驚くほど頻繁に変わります。顧問行政書士は、自らが専門とする分野の法改正については、常に最新情報を収集・分析しています。顧問契約があれば、自社に関わる重要なルール変更の情報をいち早く入手し、事業への影響を最小限に抑えるための対策を即座に打つことができます。「うっかり法令違反」という致命的なミスを避けられるのです。
4. 専門家ネットワークの「ハブ」となる
行政書士は、弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士といった他の専門家と強力なネットワークを築いています。顧問契約を結ぶことで、企業はそのネットワーク全体へのアクセス権を得られます。法務トラブルは弁護士へ、複雑な税務は税理士へ、労務問題は社労士へ。問題の種類に応じて最適な専門家を迅速に紹介してもらえる「頼れる総合窓口」が手に入るのです。
第2章:コストと節税効果を徹底比較!「社員の雇用」vs「顧問契約」
企業の成長を左右するのは、突き詰めれば「資源の最適配分」です。特に、固定費の大部分を占める「人件費」の使い方は、経営者の腕の見せ所。ここでは、「法務・管理担当の社員を1名雇う場合」と「行政書士と顧問契約を結ぶ場合」のコストを具体的に比較し、どちらが賢い投資なのかを明らかにします。
社員を一人雇うための「見えないコスト」
中堅レベルの管理担当者を一人雇う場合、会社が負担するのは月々の給料だけではありません。給与額の1.5倍から2倍近い費用がかかるのが現実です。
- 給与(年収): スタートアップや中小企業が採用する中堅担当者を想定し、年収550万円とします。
- 社会保険料など(会社負担分): 健康保険や厚生年金など、給与の約15%〜20%に相当する約82.5万円が会社の負担となります。
- 採用コスト: 人材紹介会社への手数料など、一人採用するのに平均100万円以上かかると言われています。
- 間接コスト: デスクやPC、オフィスの賃料、光熱費、研修費など、目に見えにくい費用も年間50万円以上はかかります。
これらを合計すると、年収550万円の社員一人を雇うために、会社が初年度に支払う本当のコストは約800万円にも達する可能性があるのです。
行政書士顧問のスマートな費用体系
一方、行政書士との顧問契約は、非常にシンプルかつ合理的です。
- 予測可能な顧問料: 法人向けの月額顧問料は3万円から15万円程度が一般的です。ここでは間を取って月額8万円のプランを想定します。
- 隠れたコストはゼロ: 雇用ではないため、社会保険料の負担や採用コスト、備品代などは一切かかりません。
一目でわかる年間コスト比較
| 費用項目 | 正社員(中堅レベル法務・管理担当) | 行政書士顧問(例) |
|---|---|---|
| 基本給与 / 年間顧問料 | ¥5,500,000 | ¥960,000 (月額 ¥80,000の場合) |
| 社会保険・労働保険料(会社負担分) | 約 ¥825,000 | ¥0 |
| 採用コスト(初年度) | 約 ¥1,000,000 | ¥0 |
| 間接コスト(デスク、PC、研修等) | 約 ¥500,000 | ¥0 |
| 年間総コスト(初年度) | 約 ¥7,825,000 | ¥960,000 |
| 実質的なコスト削減額 | - | 約 ¥6,865,000 |
こんな事例も!社内担当者の負担を減らし、組織全体をハッピーに
顧問契約のメリットは、コスト削減だけにとどまりません。実際に、こんなケースは少なくありません。
ある企業では、総務・法務担当者が一人で複雑な許認可や法務案件を抱え込み、連日残業が続いていました。手探りで調べて対応するため時間がかかり、業務クオリティにも課題を感じていたのです。
そこで顧問行政書士と契約したところ、状況は一変。担当者はいつでも専門家に相談できる「駆け込み寺」を手に入れ、的確なアドバイスのもとでスムーズに業務を進められるようになりました。
結果として、業務の質とスピードが劇的に向上し、担当者の残業時間は大幅に減少。担当者は早く帰れてハッピー、会社は残業代が減ってハッピー、そして業務の質も上がって顧客もハッピーという、まさに「三方よし」の状態が生まれたのです。
【経営者必見】節税と経理効率化という「ダブルのうまみ」
さらに、税金と経理の手間という面で、経営者が知っておくべき決定的な違いがあります。
1. 消費税の節税効果(仕入税額控除)
社員への給与は消費税の対象外(不課税)のため、納める消費税額から差し引くことはできません。しかし、行政書士への顧問料はサービスの対価(課税取引)なので、顧問料に含まれる消費税分を、国に納める消費税から差し引くことができます(仕入税額控除)。年間顧問料が税抜96万円なら、消費税9.6万円分の明確な節税効果が生まれます。
2. 経理の手間を劇的に削減(源泉徴収が不要)
弁護士や税理士への報酬は、支払う側が所得税を天引き(源泉徴収)し、国に納付する義務があります。これは煩雑な経理作業を伴います。しかし、行政書士への報酬は、原則としてこの源泉徴収の対象外です。企業は請求された金額をそのまま支払うだけでよく、面倒な計算や納付の手間を完全に省けます。
この差額、約700万円と節税効果、そして経理の手間削減。これらを製品開発やマーケティングといった、会社の成長に直結する活動に再投資できるとしたら? 行政書士顧問という選択は、会社の成長期間(ランウェイ)を大きく伸ばす、賢い財務戦略なのです。
第3章:【ヘルスケア企業向け】規制の壁を商機に変える「薬事戦略」
ヘルスケア分野は、人の命に関わるため、薬機法や医療法といった厳しい規制が存在します。この規制の海を安全に航海し、ビジネスを成功させるために、専門知識を持つ行政書士は事業の生命線を握る「案内人」となります。
事業の成否を分ける、薬機法・医療法への初期対応
企画段階での判断ミスは、致命傷になりかねません。
- 製品の該当性(薬機法): 開発中のアプリが、意図せず「医療機器プログラム」と判断されないか。
- サービスの該当性(医療法): 提供する健康相談サービスが、医師にしか許されない「医行為」と見なされないか。
企画の初期段階で相談することで、こうした致命的な手戻りを防ぎ、最短ルートで市場を目指せます。
許認可取得から継続的な運営までワンストップで支援
行政書士は、医療機器製造販売業許可や化粧品製造販売業許可などの複雑な申請を代行します。しかし、許認可はスタートラインです。顧問行政書士は、その後の品質管理(QMS)・安全管理(GVP)体制の運用や、保健所の立ち入り検査への対応まで継続的にサポートします。
大企業が「薬事・医事部」に担わせるこの専門機能を、スタートアップや中小企業が低コストで活用できる。これが、顧問行政書士を「社外の薬事・医事部長」と呼ぶ理由です。
第4章:【大学発スタートアップ向け】研究成果を「事業」に変える、知財戦略パートナー
大学発スタートアップの宝は、研究室で生まれた特許やノウハウという「知的財産」です。この見えない資産をビジネスとして花開かせる鍵を、行政書士が握っています。
スムーズな会社設立と事業基盤の構築
研究者が本業に集中できるよう、定款作成から会社設立、事業に必要な許認可の取得まで、煩雑な手続きをワンストップで代行します。
国の支援制度を使いこなすナビゲーター
- 創業融資の獲得: 日本政策金融公庫などに対し、説得力のある事業計画書の作成を支援し、融資実行率を高めます。
- 知財戦略のサポート: 特許庁の特許料減免制度やスーパー早期審査の活用を申請代行。さらに、大学との共同研究契約書やライセンス契約書の作成・レビューを通じて、研究成果という「宝」を法的に守り、事業化への道を整えます。
行政書士は、設立から資金調達、知財戦略までをトータルで支援し、研究成果をビジネスとして成功させるための強力な伴走者となるのです。

こちらの記事もどうぞ。外部資金調達を前提とした株式会社設立の具体的なステップと、定款作成における「4万円節約」の仕組みについてまとめています。
第5章:【全企業向け】返済不要の資金で成長を加速させる「補助金・助成金」戦略
株式を渡さずに得られる国や自治体の補助金・助成金は、経営者にとって非常に魅力的です。行政書士は、この「返済不要の資金」を獲得するためのプロフェッショナルです。
補助金獲得を「運」から「戦略」へ
- 最適な補助金の発掘: 無数にある制度の中から、自社の事業に最適で、採択可能性が高いものを的確に探し出します。
- 「採択される」申請書の作成: 審査員の視点を理解し、事業の魅力が伝わる説得力のある事業計画書・申請書類の作成を支援します。
- 採択後の面倒な報告までサポート: 採択後の実績報告まで見据え、ルール違反による返金といった最悪の事態を防ぎます。
法律で認められた「独占業務」という信頼性
法改正により、報酬を得て補助金の申請書類を作成・提出する業務は、行政書士の独占業務であることが明確化されました。これは、国が認めた専門家であるという何よりの証です。安心して任せられる専門家を選ぶことが、成功への第一歩です。
結論:あなたの会社を、次のステージへ。
これまで見てきたように、行政書士を顧問に迎えることは、単なる事務の外注ではありません。それは、会社の成長を加速させ、リスクを管理し、限りある経営資源を最大限に活かすための、非常に賢い「戦略的投資」です。
経営者が下すべき判断は、「人を雇うか、顧問を頼むか」という単純な二択ではないのです。「高コストで業務範囲が限定的な選択肢」と、「低コストで柔軟性が高く、幅広い専門知識とネットワークまで手に入る戦略的パートナー」のどちらを選ぶか、ということです。
スマートな成長を目指すすべての経営者へ。顧問行政書士は、あなたの会社の可能性を最大限に引き出し、次のステージへと飛躍させるための、最も賢い「切り札」となるはずです。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。