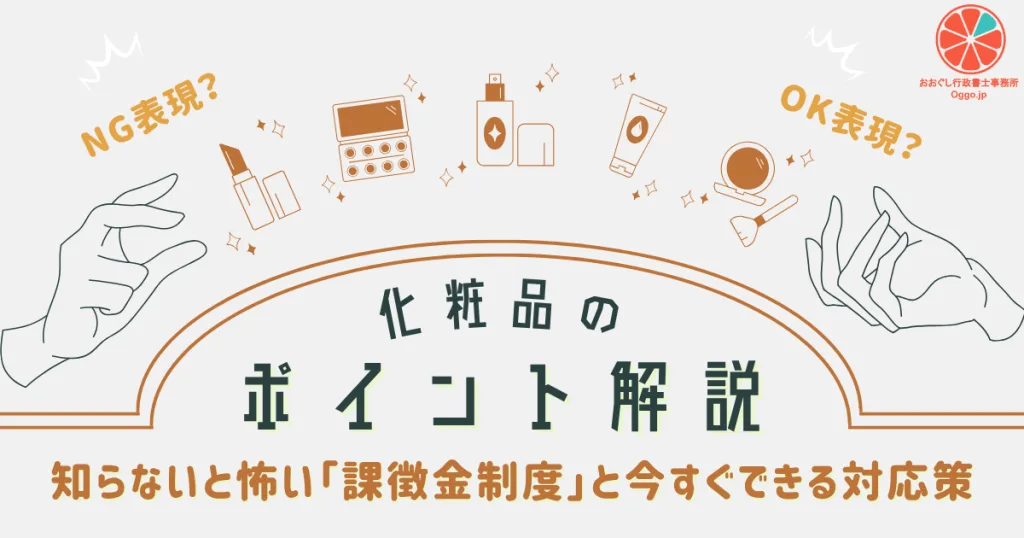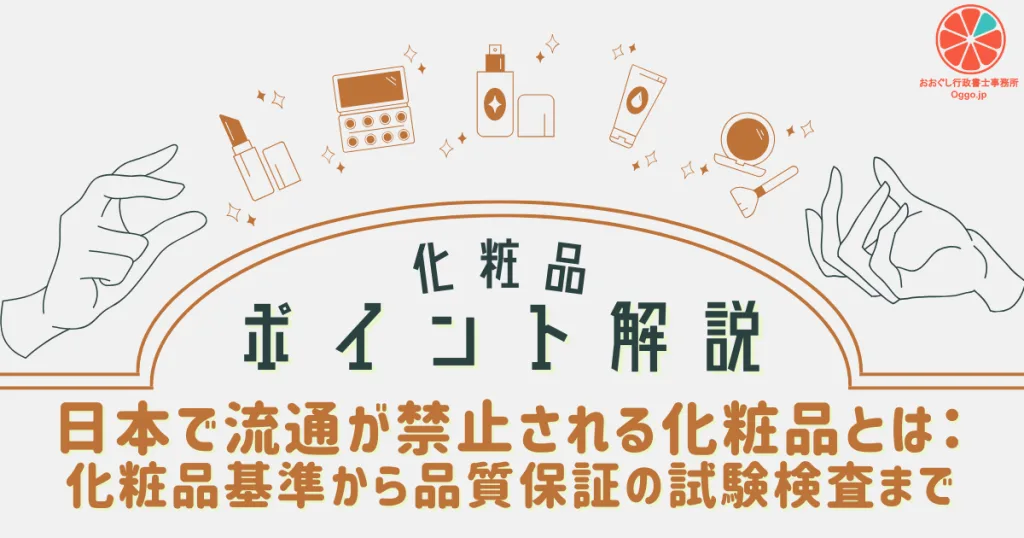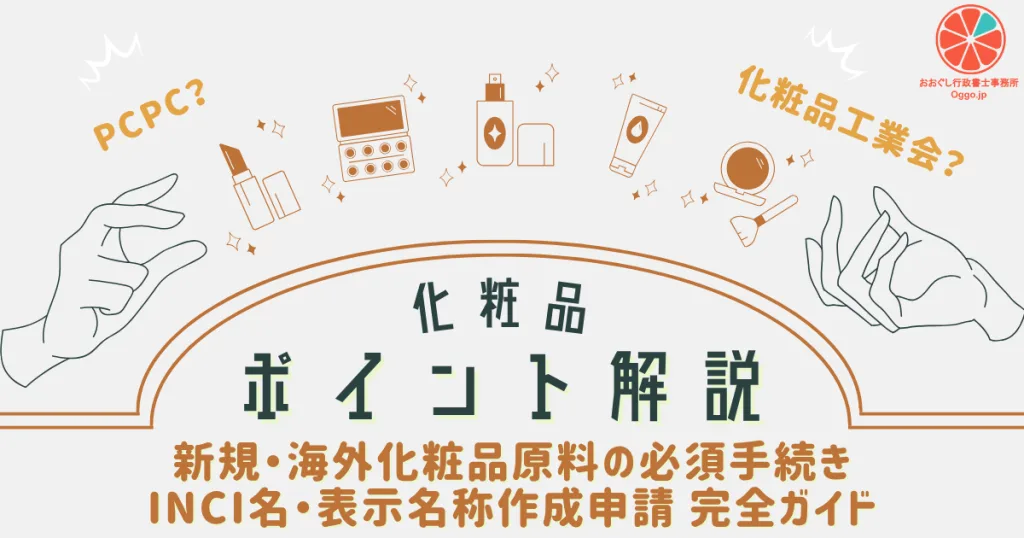化粧品広告NG表現集|薬機法と関連ガイドラインから学ぶ正しい言い換え方
「この素晴らしい製品の魅力を、一人でも多くの人に伝えたい!」その想いが強すぎるあまり、つい表現がエスカレートしてしまう。化粧品の広告担当者なら、誰もが一度は経験するジレンマではないでしょうか。
化粧品の広告は、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)と、その解釈基準である「医薬品等適正広告基準」によって厳しく規制されています。特に、化粧品でうたうことが認められている「56の効能効果」の範囲を逸脱した表現は、薬機法違反とみなされ指導の対象となりますし、課徴金などの重いペナルティの対象ともなりえます。
この記事では、日本化粧品工業会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」や、2025年3月に新たに発出された厚生労働省の通知「化粧品における特定成分の特記表示について」などを基に、マーケティング担当者が陥りがちなNG表現を具体的な事例と共に解説します。

こちらの関連記事では、課徴金制度について詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
化粧品で認められている「56の効能効果」とは
まず、全ての基本となるのが、化粧品の効能効果として広告で表現することが認められている、以下の56項目の範囲です。原則として、広告表現はこの範囲を逸脱してはなりません。
【化粧品の効能効果の範囲】
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
- (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
- 肌を整える。
- 肌のキメを整える。
- 皮膚をすこやかに保つ。
- 肌荒れを防ぐ。
- 肌をひきしめる。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 皮膚の柔軟性を保つ。
- 皮膚を保護する。
- 皮膚の乾燥を防ぐ。
- 肌を柔らげる。
- 肌にはりを与える。
- 肌にツヤを与える。
- 肌を滑らかにする。
- ひげを剃りやすくする。
- ひげそり後の肌を整える。
- あせもを防ぐ(打粉)。
- 日やけを防ぐ。
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- 芳香を与える。
- 爪を保護する。
- 爪をすこやかに保つ。
- 爪にうるおいを与える。
- 口唇の荒れを防ぐ。
- 口唇のキメを整える。
- 口唇にうるおいを与える。
- 口唇をすこやかにする。
- 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
- 口唇を滑らかにする。
- ムシ歯を防ぐ(※)。
- 歯を白くする(※)。
- 歯垢を除去する(※)。
- 口中を浄化する(歯みがき類)。
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
- 歯のやにを取る(※)。
- 歯石の沈着を防ぐ(※)。
- 乾燥による小ジワを目立たなくする。
(※使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。

こちらの関連記事では、化粧品の試験や科学的根拠の重要性について言及しています。あわせてご確認ください。
よくあるNG表現事例
これから具体的なNG・OK事例を見ていきますが、その前に、全ての広告表現に共通する最も重要な大前提についてお話しします。
それは、「表現内容は、事実であり、客観的に実証できるものでなければならない」ということです。
たとえ化粧品で認められた56の効能効果の範囲内の表現であっても、その効果が製品にない、あるいは証明できなければ、虚偽・誇大広告となります。
では、「客観的に実証されている」とはどういう状態を指すのでしょうか。厚生労働省の通知では、これを「当該効能効果や製剤技術に基づく表現として客観的に説明出来るということ」と定義しています。さらに、その根拠となる資料は「社内データであってもよいが、客観性のあるものであることが必要」とされており、製造販売業者は、いつでもその根拠を提示できるよう、責任をもってデータを保管しておく義務があります。
この大原則を踏まえ、広告を制作するライターやマーケティング担当者は、単に言葉のテクニックに走るのではなく、製品に関する正確な情報を深く理解し、真摯に表現を作成することが求められています。
1. シミ・シワ・アンチエイジングに関する表現
| NG表現 | 化粧品として認められる言い換え例 |
|---|---|
| 「シミが消える」「シワがなくなる」 | 「日やけによるしみ、そばかすを防ぐ」「乾燥による小じわを目立たなくする」 |
| 「驚きのアンチエイジング効果」「肌が若返る」 | 「年齢に応じたうるおいケア」「エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのことです」 |
【解説】「消える」「なくなる」といった表現は、化粧品で認められている効能効果の範囲を超えています。自然現象として人の肌は時間の経過によりシミ・シワが薄くなることはありえますが、商品が影響を与えたことによりそれが起きたり早まったりしたならば、それは化粧品の範囲を超えた「医薬品的な効果」とみなされます。広告は、化粧品として認められた表現内に収める必要があります。
また、「乾燥による小じわを目立たなくする」という効能効果をうたうにあたっては、日本香粧品学会のガイドラインに基づくなど、定められた方法による試験をクリアすることが要求されています。
「アンチエイジング」「若返り」もまた、化粧品の効能効果の範囲を超えています。これらの言葉を使う場合は、注釈を付けるなどして消費者が若返りを期待しない、あくまで年齢に応じたケアであると正しく理解できるよう、誤認を避ける工夫をすることが企業側に求められます。
2. ニキビ・肌質改善に関する表現
| NG表現 | 化粧品として認められる言い換え例 |
|---|---|
| 「ニキビが治る」 | 「(洗浄により)ニキビを防ぐ」※洗顔料に限る |
| 「使うだけで肌質が変わる」 | 「肌のキメを整える」「肌にうるおいを与える」 |
【解説】「治る」「治療」またはそれに類する表現は医療的であり、化粧品の範疇を超えています。化粧品で「ニキビ」という疾患に対する影響に言及できるのは、洗浄によりニキビを防ぐことが事実である場合に限られます。
「肌質改善」のような漠然としていて、かつ効果を保証するような表現はNGです。化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つため」のものであることを理解したうえで広告表現をしていく必要があります。認められた56の効能効果の範囲内で、具体的に表現していきましょう。
3. 安全性に関する表現
安全性を過度に強調する表現も、虚偽・誇大広告に該当する可能性があります。
| NG表現 | 化粧品として認められる言い換え例 |
|---|---|
| 「副作用のない化粧品」「絶対に安全・安心」 | 「パッチテスト済み」「アレルギーテスト済み」(※すべての方にアレルギーが起きないわけではありません) |
【解説】「絶対」「100%」といった表現は、万が一の可能性を否定する断定的な表現です。人には個人差というものがあり、そんなことはありえないので(「絶対」は絶対ありえない、とも言いますよね)、行った試験の事実を客観的に記載し、注釈を添えるのが適切です。
4. 第三者の推薦に関する表現
医師や専門家、有名人などの推薦を安易に使うと、薬機法違反となる場合があります。
| NG表現 | OKな言い換え例 |
|---|---|
| 「医師も推薦する〇〇クリーム」「女優の△△さん愛用だから安心」 | (原則として非推奨) |
【解説】原則として、一般の人に「この人の推薦なら、効きそうかも…」と思わせられるような人・団体による推薦は禁止されています。具体的には「医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局その他化粧品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体」が挙げられます。美容ライターや美容家の推薦は直ちに違反とはされませんが、上述のものに当てはまると判断される場合にはやはり違反となる可能性がありますので、安易に表現すべきではないと考えられます。
5. 特定成分の「特記表示」に関する表現
製品の特長として特定の成分をアピールしたい場合、「あたかもその成分が有効成分であるかのような誤認」を与えないよう注意が必要です。
「特記表示」とは、商品に配合されている成分中、特定の成分を表示することです。これには、他の文字と離したり、色を変えたり、枠で囲んだり、大きい文字にするなど、目立つように表示する場合だけでなく、広告の本文中(ボディーコピー)に成分名を記載する場合も含まれます。
このような特記表示は、消費者に「通常の化粧品より優れている」「その成分が主たる有効成分である」といった誤解を与えるおそれがあるため、原則として行うことはできません。
ただし、例外として「配合目的」を必ず併記する場合に限り、特記表示が認められています。
| NG表現の具体例 | OK表現の具体例 |
|---|---|
| ・アロエエキスを配合した化粧水です。(配合目的が記載されていないため不可) | ・アロエエキス(保湿成分) |
| ・配合目的「美肌成分」 | ・肌にうるおいを与えるアロエエキスを配合しました |
| ・配合目的「抗酸化・肌ストレス保護」 | ・ビタミンE(製品の酸化防止剤) |
| ・「生薬エキス」「漢方成分抽出物」(医薬品のような印象を与えるため不可) |
まとめ:言葉狩りではなく、本質的な魅力の表現を
薬機法の広告規制は複雑ですが、単にNG表現とOK表現のパターンを覚えればいい、というわけではありません。
化粧品の広告は、このように公開されている事例を軸足にコンセプトを理解して「消費者に誤認させない」広告をすることが何よりも重要です。消費者が広告の全体を見ているのですから、当然、規制当局も広告の全体を見て総合的に逸脱しているか否かを判断します。そうなると、文字の大小や色、イラストや写真だって関与します。
表面的な一言一句をあげつらって言い換えを探す「文字狩り」に終始するのではなく、その化粧品の本当の魅力を、誠実に、そして消費者に誤解を与えないよう工夫を凝らして表現すること。そのために頭を捻る必要があります。その真摯な姿勢こそが、お客様からの信頼を勝ち取り、ブランドを長期的に成長させる唯一の道です。

こちらの関連記事では、成分表示や名称登録に関する詳しい情報を提供しています。あわせてご確認ください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。