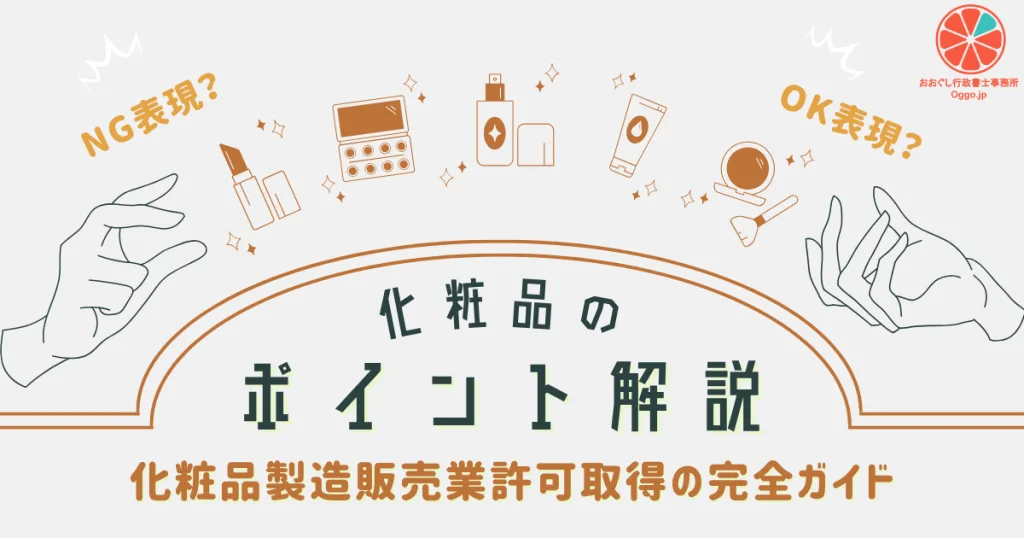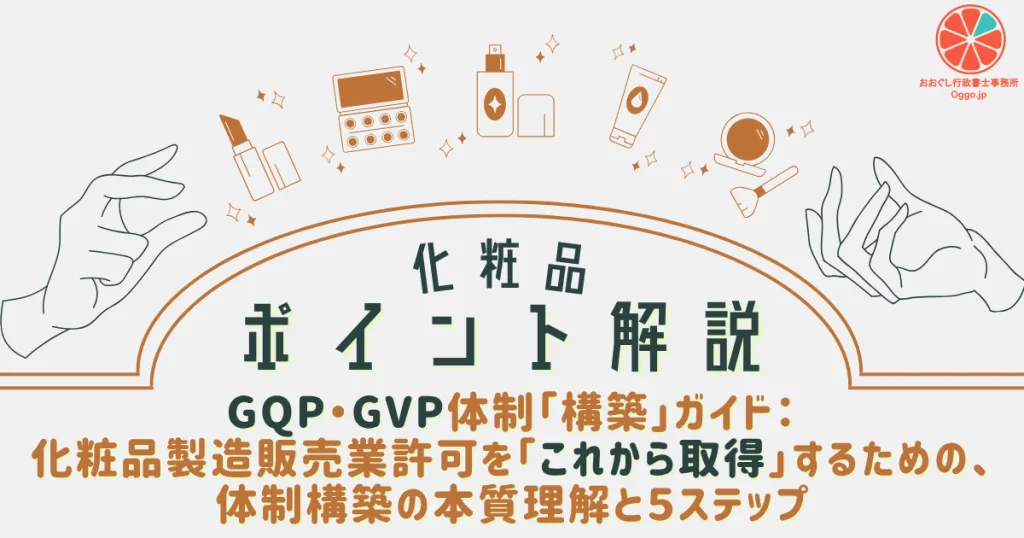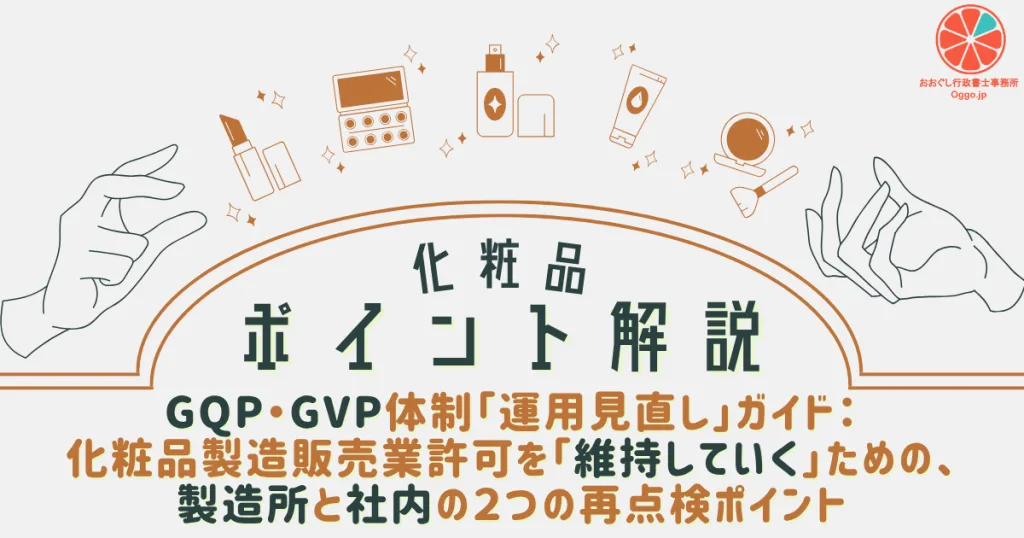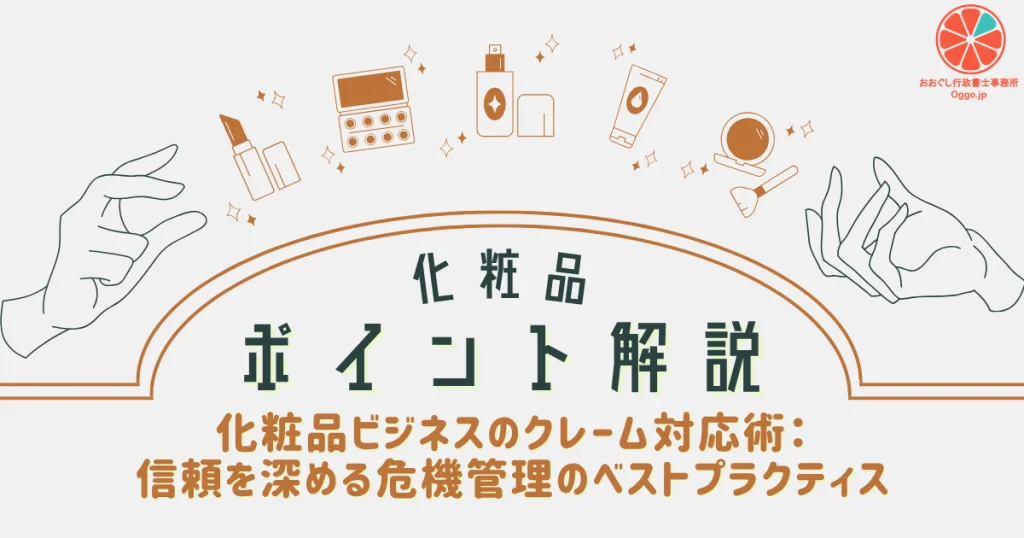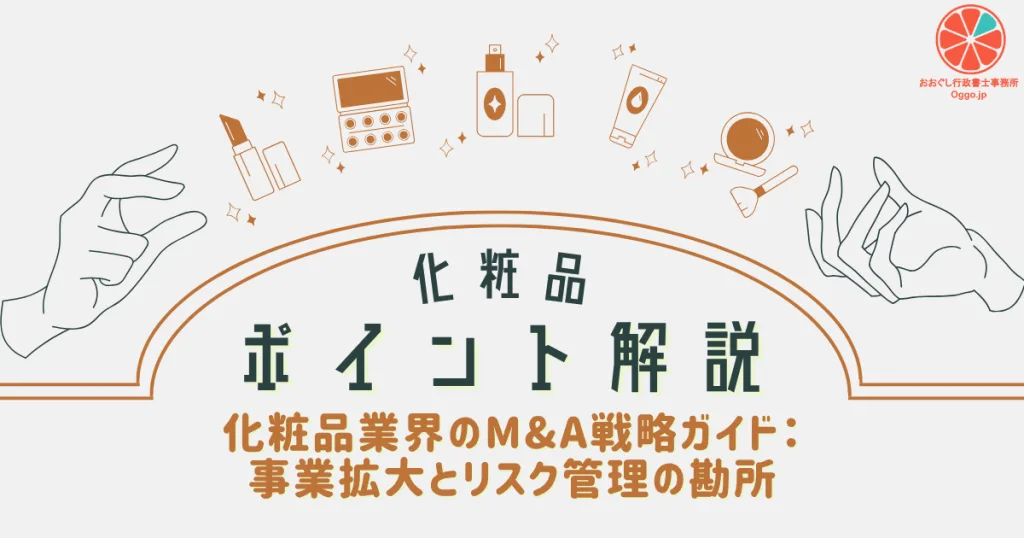化粧品OEMの2つのモデルを徹底解説!失敗しないパートナー選びと契約のポイント
「自社ブランドの化粧品を作りたい」。その夢を叶える強力な選択肢が、化粧品OEM(Original Equipment Manufacturer)です。しかし、一口にOEMと言っても、契約の形態によって自社が負うべき「責任」の重さが全く異なることをご存知でしょうか?
OEMには、大きく分けて2つのモデルがあります。
- A:自社が「製造販売業者」として法的責任を全て負うモデル
- B:OEMメーカーが「製造販売業者」となり、法的責任を担うモデル
このどちらを選択するのかが、あなたのビジネスの形、必要な許可、そして製品表示までを大きく左右します。
この記事では、2つのOEMモデルの違いを比較し、それぞれのメリット・デメリット、そしてパートナーを信頼できるかを判断するための重要なポイントを解説します。

こちらの関連記事では、製造販売業許可の取得や責任について言及しています。
どちらを選ぶ?OEMの2つの契約モデル
まず、自社がどちらのモデルでOEMを活用したいのかを明確にしましょう。
モデルA:自社が「製造販売業者」になるモデル
これは、ブランドオーナーである自社が「化粧品製造販売業許可」を取得し、製品の品質や安全性に対する全ての法的責任を負うモデルです。
- 自社の役割:「化粧品製造販売業者」として、GQP・GVP省令を遵守し、製品の最終責任を負います。製品には、自社名が「製造販売元」として表示されます。
- OEMメーカーの役割:「化粧品製造業許可」を持つ「製造業者」として、自社の指示と取り決めに従って製品を製造します。
モデルB:OEMメーカーが「製造販売業者」になるモデル
これは、OEMメーカー自身が「化粧品製造販売業許可」を保有しており、そのOEMメーカーが製品の法的責任を負うモデルです。
- 自社の役割:「ブランド企画者」「委託者」として、製品のコンセプトや販売戦略を担います。製品の法的責任は負わないため、「化粧品製造販売業許可」は不要です。(ただし、道義的責任やレピュテーションリスクは当然別の話ですのでご注意を。)
- OEMメーカーの役割:「製造販売業者」として、製品の品質・安全性に関する全ての法的責任を負います。製品には、OEMメーカーの会社名を「製造販売元」として表示することが必須です。自社名は「発売元」などとして任意で表示することが可能です。
各モデルのメリット・デメリットを比較
どちらのモデルが自社に適しているか、以下の比較表で検討してみましょう。
| モデルA:自社が製造販売業者 | モデルB:OEMメーカーが製造販売業者 | |
|---|---|---|
| メリット | ◯ ブランドの全権を掌握できる ◯ 製品に自社名のみを表示できる ◯ 複数のOEMメーカーを自由に使える | ◯「製造販売業許可」が不要で参入が容易 ◯ GQP/GVP等の法的責任を委任できる ◯ 薬事に関する専門人材が不要 |
| デメリット | ✕ 「製造販売業許可」の取得・維持が必要 ✕ GQP/GVP体制の構築・運用コストがかかる ✕ 専門人材(総括など)の確保が必要 | ✕ ブランドのコントロール権が弱い ✕ 製品にOEMメーカー名が表示される ✕ パートナーの変更が困難 |
失敗しないOEMパートナー選びの【最重要】ポイント
信頼できるOEMメーカーを選ぶための視点は、両モデルで共通する部分と、モデルごとに特に注意すべき部分があります。
共通のチェックポイント
以下はモデルAでもモデルBでも共通の確認事項です。
- 実績と得意分野: スキンケア、メイクアップ、ヘアケアなど、自社が作りたい製品カテゴリでの開発・製造実績が豊富かを確認しましょう。
- 対応ロット数とコスト: 自社の事業計画に見合ったロット数とコストで生産が可能かを確認します。
- 品質管理体制のレベルを見極める: 契約を結ぶ前に、品質管理に関する社内文書(手順書など)や業務フローを見せてもらう、あるいは工場見学を申し出て、実際の管理レベルを自分の目で確かめることが極めて重要です。整理整頓の状況や従業員の品質への意識なども、信頼性を測る上で参考になります。できるならば、薬事業務の管理者経験がある人と一緒にチェックリストを作って見学に臨むと、雰囲気に流されずに適切に判断しやすくなるでしょう。
【モデルA】での最重要注意点:GQPに基づく3つの必須アクション
自社が「製造販売業者」となるモデルAでは、自社には、OEMメーカー(製造業者)に対し品質を確保するための具体的な管理監督を行う責任が生じます。特に以下の3つのアクションは法的に必須です。
- 「OEM契約書」と「取決め書」を締結する: 一般的なビジネス条件を定める「OEM契約書」とは別に、製造販売業者には、GQP省令第7条に基づき、製造業者との間で品質管理に関する詳細な「取決め書」を文書で締結する法的義務があります。
- 製品ごとに「製品標準書」を入手する: その製品の品質に関する全ての基準(製造手順、規格、試験方法など)をまとめた「製品標準書」を、OEMメーカーから品目ごとに必ず入手します。これは、自社が製品の品質を保証するための拠り所となる重要な文書です。
- 約束通りか「実地での監督・視察」を行う: 取決めや製品標準書の内容通りに製造・品質管理が行われているかを、定期的に実地で確認(視察・監査)する必要があります。書類上だけでなく、実際の現場を見て監督することが、製造販売業者としての責任です。
これらの必須アクションに対して、誠実かつ積極的に協力してくれるかどうかが、パートナーとして信頼できるかを判断する最大のポイントです。

こちらの関連記事では、GQP省令に基づく「取決め書」や「製品標準書」について言及しています。
【モデルB】での最重要注意点:相手は信頼できる「製造販売業者」か
モデルBでは、自社ブランドの品質と安全性をOEMメーカーに委ねることになります。したがって、相手が信頼に足る「製造販売業者」であるかを、より一層厳しく見極める必要があります。
- GVP(製造販売後安全管理)の運用実績: お客様からのクレームや副作用情報など、市販後の安全情報をどのように収集・検討し、対応してきたか、具体的な運用実績を確認しましょう。
- トラブル発生時の対応力: 万が一、製品に問題が発生した場合の報告体制、原因究明、顧客対応、回収などのプロセスが明確になっているかを確認します。
- 契約内容の精査: 責任の所在(どこまでがOEMメーカーの責任で、どこからが自社の責任か)を契約書で明確に定めておくことが不可欠です。

こちらの関連記事では、GVPの運用実績やトラブル対応力について言及しています。
まとめ
化粧品OEMメーカーに協力を求めることは、化粧品事業を形にするための強力なカードです。しかしゲームに勝つためには、自社の戦略に合ったモデルを選択し、信頼できるパートナーを見つけられるかにかかっています。
- ブランドの主導権を握り、将来の拡張性も考えるなら「モデルA」
- まずはスピーディーに市場に参入したいなら「モデルB」
どちらの道を選ぶにせよ、パートナー候補の品質管理体制や法規制への理解度を徹底的に見極めること。そして、単なる「委託先」ではなく、ブランドの価値とお客様への責任を共有できる真の「パートナー」を、ぜひ見つけ出してください。

実はOEMパートナー選びは、企業買収のデューデリジェンスが参考になりますので、こちらもあわせて御覧ください。

お気軽にご相談ください。
- 初回相談は無料です。
- 行政書士には秘密保持の義務が課せられております。
- フォームに入力されたメールアドレス以外に、当事務所から連絡差し上げることはいたしません。